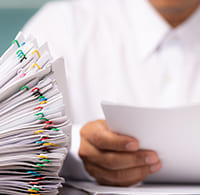遺言作成の基礎知識と適切な執行のヒント
「自分で本を見ながら遺言書を作ってみたけれど難しい」「遺言が有効ではなかったらと思うと不安」
法的に有効な遺言を、個人で自力で作成するのは簡単ではありません。遺言作成に先立つ財産調査から確実な遺言執行まで、弁護士ならではの観点でアドバイスいたします。
ただ遺言を作る・チェックするだけではなく、当事務所の過去の豊富な実績を活かし、後で揉めない相続のために、お客様の親身になって対応いたします。
↓遺言作成に関わる、問題解決に役立つヒントや基礎知識についてご紹介します。
遺言書とは

遺言書とは、自分の遺産等について最後の意思表示をするものになります。 通常、法定相続分に沿って遺産分割協議を進めますが、遺言書を作成することによって遺産の行き先を自由に決めることができます。 ただし、被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人には遺留分が存在しますで、予め確認しておきましょう。
3種類の遺言について

遺言書には自筆遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3つがあります。 自筆遺言書は、自身で作成から管理まで行えて費用が掛かりません。公正証書遺言は、法律の専門家が作成するため争いになりづらく、秘密証書遺言は、自筆ではなくパソコン・代筆で作成しても効力を発揮します。 それぞれにメリット・デメリットが存在しますので詳しく押さえておくようにしましょう。
公正証書遺言作成の流れ

公正証書遺言の作成をするにあたり、はじめに必要書類の収集を行います。次に公証人と内容のすり合わせをし、事前協議を行います。 次に遺言書作成の日時と証人の選定を行い、最後に、公証役場で遺言者が趣旨を公証人に口述し、公証人が作成を行います。公証人が口頭で遺言者と証人に読み聞かせ、問題が無ければ遺言者と証人が署名押印を行って終了します。
遺言書作成時の財産調査
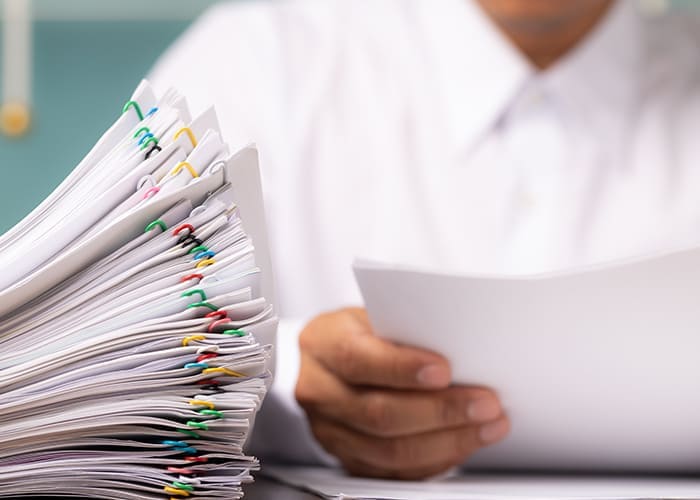
遺言書を作成する際、事前に財産調査をしておく必要があります。 例えば、生命保険金の受取人が約款で指定されていない場合、相続人全員が受取人となり遺産分割協議が発生します。その他にも、土地や不動産の評価額で遺留分の金額が変わります。いずれも大きな影響がありますので、遺言作成時の財産調査について予め確認しておきましょう。
遺言の執行

遺言執行者とは、遺言者による指定、または家庭裁判所から選任された方のことを指し、遺言書に記載された内容を実現する権利義務を有する方のことを指します。 また、遺言執行者の報酬については、遺言書で定める、家庭裁判所が定める、相続人と遺言執行者で協議して定める場合等があります。
保管と検認

遺言書の作成後、自身で遺言書を管理をしているような場合、一定の相続人が有利になるように改ざん・破棄などを行われる可能性があります。また、作成した遺言書を相続人に見つけてもらうことができなければ効力を発揮することができません。このページではこれらへの対策をご説明していますのでご確認ください。
遺言の取り消し

何らかの事情により、遺言書の内容を訂正・加筆をしたい場合は、新たな遺言書を用いて行うことが可能です。この際、 民法968条2項の規定に基づいて変更を行う必要があります。また、先に作成したものが公正証書遺言で、次に作成したものが自筆証書遺言でも問題ありません。気になる方は詳しくご参照ください。
遺言作成に関する費用
| 内容 | 項目 | 費用(税込) | |
|---|---|---|---|
| 遺言書作成 | 作成報酬金 | 22万円~ (出張の場合、別途日当が生じます) |
|
| 遺言書保管 | 年間保管料 | 1.1万円 | |
| 遺言執行 | 300万円以下の場合 | 報酬金 | 33万円 |
| 300万円を超え、3,000万円以下の場合 | 報酬金 | 26.4万円+遺産総額×2.2% | |
| 3,000万円を超え、3億円以下の場合 | 報酬金 | 59.4万円+遺産総額×1.1% | |
| 3億円を超える場合 | 報酬金 | 224.4万円+遺産総額×0.55% | |
- ① 遺言書作成:簡明な遺言書作成(財産の多寡、推定相続人の数、遺言の内容等から判断致します。)の場合は、上記手数料から減額することがあります。
- ② 遺言書保管:遺言書にて当事務所が遺言執行者に指定された場合には、遺言書保管費用はいただきません。
遺言作成に関するよくある質問
遺言作成に関する当事務所の弁護士監修コラム


遺言で受取人を変更できる?遺産・保険金について確認しよう

遺言で赤の他人に財産を譲ることはできる?注意点とともに解説
その他の相続分野