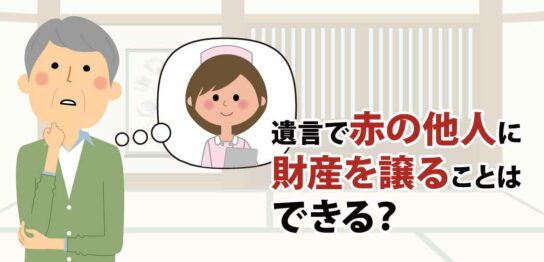- 遺言書によって相続分の指定ができる
- 遺言書の内容に納得できない場合は、相続人全員の合意で遺言書の内容と異なる遺産分割協議をすることも可能
- 遺言書を無効と主張できる場合・遺言書が有効でも遺留分侵害額請求ができることも確認
【Cross Talk 】遺言書がある場合、絶対にその通りにしないとダメなのか?
先日父が亡くなり、遺言書が見つかったのですが、遺産分割の内容を指定したもので、実はその内容に、相続人一同が納得できないのです。相続人全員が納得しているならば、遺言書の存在をなかったことにできませんか?
相続人全員が同意しているのであれば、遺言書に反する遺産分割ができる場合もあります。そうでない場合であっても遺留分侵害額請求ができる場合があるので、あわせて確認しておきましょう。
納得のいかない遺言書がある場合は、遺言書の無効を主張することが考えられます。 しかし、遺言書の無効を主張できる場合は実際かなり少ないです。遺言書が有効であるとして、相続人で話し合って遺言書の内容と異なる遺産分割協議はできないでしょうか? 遺言書が有効で、かつ、遺言書の内容と異なる遺産分割協議ができない場合は、遺留分侵害額請求をすることも視野に入れましょう。
遺言書が無効であるというためには

- 遺言書が無効であるというためには
そもそも、今回の遺言書は無効ではないか?という争い方はできませんか?
遺言書が無効と評価される場合を知っておいてください。
遺言書が無効であるという主張をするのは、どのような場合が想定されるのでしょうか。
遺言書が有効である要件
前提として、遺言書が有効であるための要件としては、次のような要件が必要です。15歳以上であること
民法961条は15歳に達した者であれば遺言書を作成することができるとしています。 そのため、遺言者は15歳を超えている必要があります。遺言能力があること
遺言者に遺言能力があることが必要です。 遺言能力とは、自己の遺言書でどのような効果が発生するのか、弁識するに足りる能力のことをいいます。 高齢や認知症が原因で判断能力が無くなってしまうと、遺言能力が無くなってしまうので、遺言書は無効となります。 高齢や認知症となった場合に成年後見人が選任されますが、成年後見人が選任されていることと、遺言能力の有無は、別の要件です。成年被後見人の場合に意思を回復している場合は医師2名の立ち会い
成年被後見人が、事理を弁識する能力を一時回復した時は、医師2名の立ち会いのもとで遺言書の作成ができます(民法973条)。 立ち会った医師は、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記(秘密証書遺言の場合には封紙に記載する)する必要があります。被後見人は、後見人等に利益になるべき遺言書を作成する場合、後見の計算が終わった後にすること
被後見人が、後見の計算の終了前に、後見人・後見人の配偶者・後見人の子ども・孫などに対して利益となる遺言書を作成したときは、その遺言書は無効とされます。(民法966条1項) 後見人は被後見人の財産処分について影響力を持っているため、このような遺言書を強いることがないように規定が置かれています。 そのため、例えば被後見人であった人が、後見人に銀行預金を遺贈するという遺言書を作成する場合は、後見の計算が終了した後でなければなりません。 なお、後見人が直系血族、配偶者又は兄弟姉妹である場合は、この規定は適用されません。(民法966条2項)自筆証書遺言
自筆証書遺言を作成する場合は、全文、日付及び氏名を自書し、押印する必要があります。(民法968条1項) なお、財産目録については、パソコン・ワープロで作成することが認められています。(民法968条2項) 訂正がある場合は、訂正箇所を指示して変更した旨を記載し印鑑を押さなければなりません。(民法968条3項)公正証書遺言
公正証書遺言をする場合は、民法969条各号所定の次の要件を満たすことが必要です。- 証人二人以上の立会い
- 遺言者が遺言書の趣旨を公証人に口授する
- 公証人が、遺言者の口述を筆記し、筆記した内容を遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させる
- 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認して署名捺印する
- 公証人が署名捺印する
秘密証書遺言
秘密証書遺言をする場合は、民法970条所定の次の要件を満たすことが必要です。- 遺言者が、その証書に署名捺印すること。
- 遺言者が、その証書に封をして、証書に押印した印鑑で封印すること。
- 遺言者が、公証人1人と証人2人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。
- 公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載し、遺言者及び証人とともにこれに署名捺印すること。
特別方式の遺言
自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の他にも、次の4つの特別方式の遺言が認められています。| 方式 | 要件 |
|---|---|
| 一般危急時遺言 | ・疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者 ・証人3人以上の立会い ・証人のうち1人に遺言書の趣旨を口授する ・口授を受けた者がこれを筆記して遺言書他の証人に読み聞かせ、閲覧させる ・各証人が筆記が正確なことを承認した後署名捺印する |
| 船舶危急時遺言 | ・船舶が遭難 ・船舶中に在って死亡の危急に迫った者 ・証人2人以上の立会い ・口頭で遺言 ・証人が趣旨を筆記して署名・押印 ・証人の1人又は利害関係人から遅滞なく家庭裁判所に請求して確認を得る |
| 一般隔絶地遺言 | ・伝染病のため行政処分によって隔絶地にある人 ・警察官1人及び証人1人以上の立会い |
| 船舶隔絶地遺言 | ・船舶中に在る人 ・船長又は事務員1人および証人2人の立会い |
遺言書の内容が公序良俗に反しない
遺言書の内容が公序良俗に反しないことが必要となります。(民法90条)。遺言書が無効となる場合
遺言書が無効となる場合は、次のようなことケースがあげられます。遺言能力がない
遺言書を作成した当初、既に高齢・認知症などで遺言書の内容を弁識する能力が無くなっているような場合には、遺言能力がないと判断され、遺言書は無効となります。 公正証書遺言で遺言書が作成された場合であっても、遺言能力が否定された事例もあるので注意が必要です。自筆証書遺言の要件を満たさない
全文を自書しなかった場合や、自書した場合でも、例えば日付を「○○年○月吉日」などと曖昧な記載を行ったような場合には、日付の記載がないと評価されるような場合に、遺言書は無効となります。 自筆証書遺言は専門家によるチェックを経ずにされることも多く、無効となることが多いので注意が必要です。公正証書遺言の要件を満たさない
証人適格のない人が証人となって秘密証書遺言が作成されたなど、公正証書遺言の要件を満たさない場合、遺言書は無効となります。 公正証書遺言は公証人という専門家が遺言書を作成するために、方式に沿わないとして無効となる状況はあまり考えられません。秘密証書遺言の要件を満たさない
例えば、日付の記載がない、証人適格のない人が証人になったなど、秘密証書遺言の要件を満たさない場合には、遺言書が無効となります。特別方式の遺言の要件を満たさない
証人が証人適格を満たしていなかったり、記名・押印がなかったりすることで、特別方式の各要件を満たさない結果、遺言書が無効 になることがあります。遺言書の内容が公序良俗に反する
事実婚のような実態がないにも関わらず、不倫相手に全財産を遺贈する旨の遺言書が作成されているなど、遺言書の内容が公序良俗に反する場合に遺言書が無効となります。遺言書の無効を主張するための方法
遺言書の無効はどのように主張すべきでしょうか。 まずは、相続人や、遺言書の内容に利害関係を有する当事者と、遺言書の有効性について話し合うこととなります。 この話し合いに関しては、特に手続きに関する規定はありませんので、任意の方法で話し合います。何を理由に遺言の無効を主張するかにもよりますが、遺言能力について争う場合は、遺言書には必ず作成した日付が記載されていますので、その時点で遺言者が認知症を患っており、正常な判断ができる状態になかったことを示すために、医師の診断書を得るなどします。
遺言書の内容に利害関係を有する当事者の誰かが、遺言書が無効であることを認めないような場合は、裁判所に遺言無効確認の訴えを提起して、裁判所に遺言書が無効であることを確認する旨の判決を出してもらいます。遺言書が有効だった場合の遺言書と異なる遺産分割協議

- 遺言書が有効である場合のその内容と異なる遺産分割協議の可否
そもそも遺言書がある場合に、その内容に反する遺産分割協議をすることはできるのでしょうか。
遺言書で禁じていない、相続人が全員同意しているという事情があれば、可能である場合があります。
そもそも遺言書がある場合、その内容に反する遺産分割協議ができるのでしょうか。 以下3つの場面に分けて考えてみましょう。
遺言執行者が選任されていない場合
遺言書は、被相続人の最後の意思表示であり、基本的には尊重されるべきなのですが、その内容次第で相続人が逆に困ってしまうということも有り得ます。 そのため、民法は第907条で、遺言書で禁止をしていない限り、遺言書があっても協議で遺産分割をすることができる としています。したがって、遺言書で禁止をしていない、相続人全員が同意をしている、といった場合は遺言書の内容に反する遺産分割協議をすることができます。
遺言執行者が選任されている場合
遺言書を作成する人の中には、相続財産が多岐にわたる方もいらっしゃいます。 相続財産が多岐にわたる場合は死後、遺言書に関する事務を行う「遺言執行者」を選任することがあります。 遺言執行者がついた場合は、遺言執行者の業務執行を相続人が妨げることはできないとされていますので(民法第1013条)、遺言執行者の同意がなければ、遺言書の内容と異なる遺産分割はできません。遺贈がある場合
相続人以外の第三者に対して遺産を譲渡する旨の遺言書を作成することを、遺贈といいます。 遺贈には、特定の財産(不動産・自動車など)を指定して遺贈をする場合と(特定遺贈)、割合を指定して遺贈する方法(包括遺贈)があり、包括遺贈がされている場合は、受遺者も同意しなければ遺産分割をすることができません。遺言書の内容が遺留分を侵害している場合

- 遺言書が有効でも遺留分を侵害している場合は、遺留分侵害額請求が可能
- 遺留分侵害額請求の流れ
遺言書が無効とはいえない場合は、何も主張できなくなりますか?
遺言書の内容が有効でも、遺言書が遺留分を侵害している場合には、遺留分侵害額請求をすることができる場合があります。
遺言書の内容が無効とはいえない場合でも、遺言書が遺留分を侵害している場合は、遺留分侵害額請求をすることが可能です。
遺留分とは
遺留分とは、相続において最低限保障されている権利のことで、兄弟姉妹以外の相続人に保障されているものです。 具体的には相続分の1/2(直系尊属のみが相続人である場合には1/3)が遺留分として保障されています。遺留分侵害額請求をする
生前贈与や遺贈によって遺留分に相当する遺産を受け取れなかった人は、生前贈与の受贈者・遺贈の受遺者に対して遺留分侵害額請求をすることができます。遺留分侵害額請求の流れ
遺留分侵害額請求は、遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間権利行使しなければ時効にかかるため、1年以内に権利行為をする必要があります。 1年以内に権利行使したことを証明できるようにするため、内容証明郵便で請求をします。 その後相手と交渉をして、支払いに関する交渉を行います。 任意で支払いをしない場合には、調停・訴訟によって支払いを求めることとなります。まとめ
このページでは、遺言書がある場合に、遺言書の内容に反した遺産分割協議ができるかどうかについてお伝えしてきました。 基本的には「関係者が全員同意していればできる」と考えていただいたうえで、遺言書の内容で遺言執行者が指定されている場合、遺贈されている場合に、同意を得る対象が異なってくると考えておけば良いでしょう。

この記事の監修者
最新の投稿
- 2024.03.22相続手続き代行遺産相続を弁護士に相談・依頼したときの流れ、準備することを解説!
- 2023.09.17遺言書作成・執行遺言書は誰に預ける?危険のない方法について弁護士が解説
- 2023.07.18相続全般独身の人が亡くなったら法定相続人は誰になる?注意点についても弁護士が解説
- 2023.07.18遺言書作成・執行遺言書に納得できない!遺言書と異なる遺産分割はできる?
無料