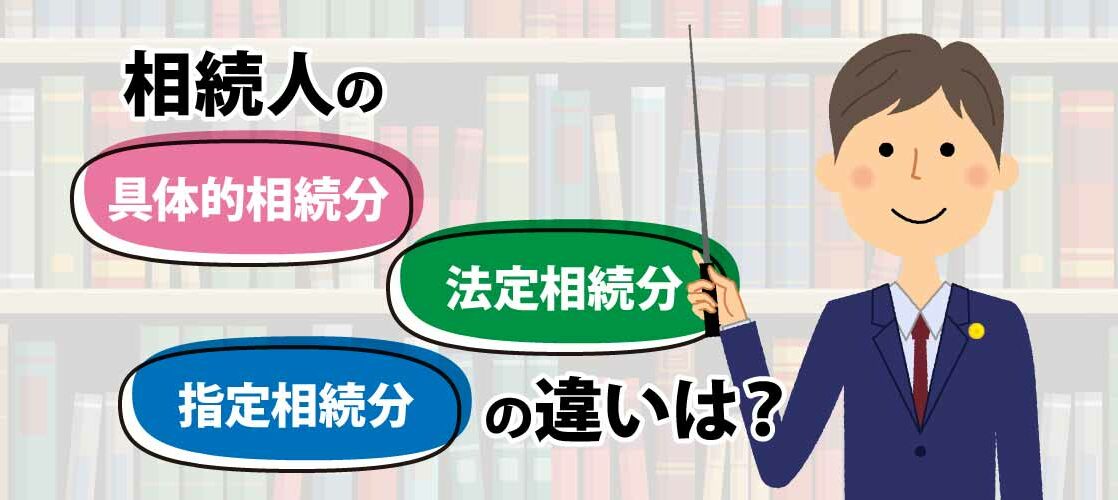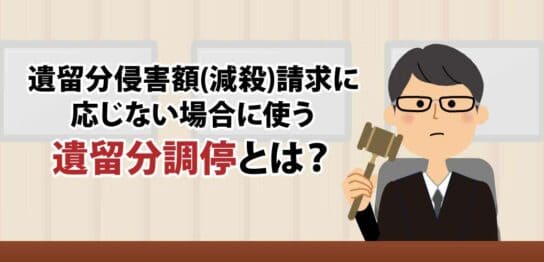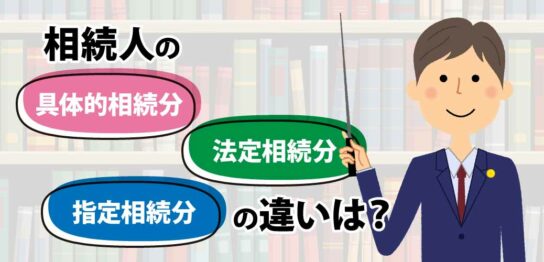- 法定相続分指定相続分・具体的相続分の言葉の意味
- 計算の仕方
- 不動産がある場合の分割方法
【Cross Talk】相続分という名前のいくつかの用語がわかりづらい
先日父が亡くなり、母と兄と私で相続をすることになりました。手続きについて調べて欲しいと任されているのですが、相続分について、法定相続分・指定相続分・具体的相続分と様々な「相続分」という言葉がありややこしくなっています。
そうですね。言葉にはなれていないと少し難しいかもしれません。順番に把握した上でどうやって計算するかについても見てみましょう。
誰がどのように相続をするかについて、「法定相続分」「指定相続分」「具体的相続分」という言葉があります。それぞれ「相続分」という言葉がついているのですが、シチュエーションによって使う言葉が異なってくるので把握しておきましょう。そのうえで、それぞれの計算をどのようにするか?ということも併せて見てみましょう。
法定相続分とは?

- 法定相続分とは民法の規定に沿った相続分
- 誰が相続人か、誰にどの程度の遺産を譲ることになるのかの目安になる
まず「法定相続分」とはどのようなものですか?
相続が発生したときに民法の規定にそって、誰にどの程度の相続分があるのか、誰にどの程度の遺産を譲るかの目安となる相続分です。
指定相続分とは?

- 指定相続分とはどのようなものか
- 指定の方法
次に「指定相続分」とはどのようなものなのでしょうか。
遺言書で遺産分割の方法を指定することができ、その指定によって決まった相続分のことを指定相続分といいます。
指定相続分とは?
上述した法定相続分は、遺言書なくして被相続人が死亡したときの相続分になります。 一方、指定相続分は、遺言書の中で遺言者が相続分を指定した際の相続分となります。 遺言者は遺言書で、誰がどのような割合で相続をするか指定をすることができ、その指定がある場合には、民法の規定と異なる相続分で相続を行います。 相談者の場合では、妻1/2・子どもがそれぞれ1/4ずつの法定相続分がありますが、遺言書で妻が1/4・長男が1/2・長女が1/4と指定することも可能です。指定相続分の決め方
指定の内容については、遺言書でどのような割合にするかを決めておくことができます。 また、遺言書の指定を特定の方に依頼しておいて、亡くなってからその依頼した方に相続分の指定をしてもらうこともできます。相続分を指定する場合には遺留分を侵害する可能性があるので注意が必要
相続分の指定を自由にすることができるので、例えば長男が全て継ぐべきだと、遺言書で指定相続分を10割長男にすることも可能です。 ただし、この場合、妻・長女はこの相続の指定により遺留分を侵害されているため、長男に対して遺留分侵害額請求をすることができます。 遺留分を侵害しないような遺言書を残すのか、遺留分侵害額請求に対応することができるお金を用意するのか、いずれにせよ配慮はしておくべきでしょう。 遺留分については「遺言をした結果親族が紛争状態に?そうならないための遺留分の基本的な知識をチェック」こちらで詳しく解説しておりますので参照してください。具体的相続分とは?

- 具体的相続分とは?
- どのような修正要素があるのか
次は「具体的相続分」について教えてください。
法定相続分はどのような家族でも適用されるものなのですが、家族の中には被相続人と生活を共にしていて介護などにつとめた人もいれば、一人だけ私立の医学部に行かせてもらった、住宅ローンの資金をもらった、というような事情もあります。このような具体的事情による修正をしたものが具体的相続分です。
具体的相続分の計算方法

- 具体的相続分の計算方法
法定相続分の微調整をした後の相続分が具体的相続分というわけですね。具体的にはどのような制度があり、どう計算するのでしょう。
寄与分・特別受益といった制度とあわせて、最初からどうやって計算をしていくか確認しましょう。
相続人の確定
まず相続人が誰であるかを確定します。 被相続人の、生まれてから亡くなるまでの戸籍を取り寄せて、相続人になる方が誰なのかを確定します。 戸籍の取り寄せ方については「相続したときに必要な戸籍謄本の取り方・見方・提出先について解説」こちらで詳しくお伝えしています。法定相続分の確定
相続人が誰なのかを確認し、民法の規定に沿って法定相続分を確定します。特別受益を確定
次に、特別受益について確定します。 特別受益とは、生前に被相続人から利益を得ているような場合で、上述した私立の医学部を卒業するための費用、不動産を取得するための費用などが挙げられます。 このような費用がある場合には、特別受益分を遺産に足したうえで、特別受益者の法定相続分から差し引きます。寄与分を確定
次に、寄与分を確定します。 寄与分とは、生前に被相続人の遺産の形成に対する寄与があった場合、その分についてはその者に相続分を上乗せする制度です。 例えば、被相続人が高齢になってから介護が必要な場合に、ヘルパーなどを利用せずに相続人がつきっきりになっていたような場合には、ヘルパーにかかったとみられる費用分の遺産が減らなかったといえます。 寄与分があるときには、遺産から寄与分を差し引いて、その分を相続人の具体的相続分に上乗せします。具体的相続分の例

- 具体的相続分の例
計算式はよくわかりました。実際にはどのように計算されるのでしょうか?
実際の計算方法を確認しましょう。
具体的相続分の実際の計算方法を確認しましょう。
具体的相続分の計算例
まず、特別受益も寄与分もない場合には、法定相続分を計算します。 相続財産が2,000万円で、母・子ども2名で相続したとします。 相続割合は母1/2・子どもがそれぞれ1/4ずつです。 そのため、母:(2,000万円✕1/2)=1,000万円
子ども:(2,000万円✕1/4)=500万円
が法定相続分となります。 特別受益・寄与分が問題にならないのであれば、相続割合で計算したこの金額がそのまま具体的相続分となります。
特別受益がある場合の計算例
特別受益がある場合には具体的相続分は次の通りとなります。 同じように、相続財産が2,000万円で、母・子ども2名で相続したとして、子どものうち一人(Aとします)が500万円の生前贈与を受けていたとします。この場合、まず特別受益を加算した「みなし相続財産」を計算します。
相続財産2,000万円+特別受益500万円=みなし相続財産2,500万円
次にこの2,500万円をもとに法定相続分で分割し「一応の相続分」を計算します。
- 母:2,500万円✕1/2=1,250万円 子ども:2,500万円✕1/4=625万円
- 母:1,250万円
- A:625万円-500万円=125万円
- 子ども:625万円
相続財産2,000万円-寄与分500万円=みなし相続財産1,500万円
次にこの1,500万円をもとに法定相続分で分割し「一応の相続分」を計算します。
・子ども:1,500万円✕1/4=375万円
・B:375万円+500万円=875万円
・子ども:375万円エラー! ハイパーリンクの参照に誤りがあります。
具体的相続分が決まっても不動産がある場合には分割方法についても決めなければならない

- 不動産がある場合の処理
具体的相続分についてはわかったのですが、父の遺産はそのほとんどが不動産なんですが、この場合どう分ければ良いのでしょうか。
不動産がある場合の処理を確認しましょう。
具体的相続分が決まらない場合には弁護士に相談する

- 具体的相続分が決まらない場合の解決方法として弁護士に相談する
具体的相続分がなかなか決まらない場合にはどうすればいいでしょうか?
やはり弁護士に相談してもらいたいです。その理由をお伝えしますね。
具体的相続分が決まらない場合には弁護士に相談しましょう。
公平な遺産分割が可能となる
具体的相続分が決まらないような場合には、公平な遺産分割を行うための計算方法がわからないというのが原因であることが多いです。 弁護士に相談すれば、この計算を正確に行い、公平な遺産分割が可能となります。スムーズな遺産分割が可能となる
具体的相続分が当事者で決められないような場合、どうしても時間がかかってしまいます。 相続税申告が必要な場合には、小規模宅地等の特例など、遺産分割が済んでいないと受けられない相続税の優遇措置が受けられなくなる可能性もあります。 弁護士に相談して、交渉のポイントを把握すれば、スムーズな遺産分割が可能となります。相続人の間での争いが軽減される
相続人の間での争いが軽減される可能性があります。 具体的相続分の意見の食い違いなどから、相続人の間での争いに発展してしまうことがあります。 一度争いに発展してしまうと、相続人同士の仲が険悪になってしまいかねません。 弁護士に相談し、依頼して交渉を任せれば、面と向かって争うことがなくなり、相続人の間での争いが軽減されます。まとめ
このページでは、法定相続分・指定相続分・具体的相続分という言葉の意味についてお伝えしてきました。 実際には、特別受益・寄与分の細かい算定が必要となるため遺産分割がうまくいかないような場合もあります。具体的相続分の計算に迷ったときには、弁護士に相談するようにしてみましょう。

この記事の監修者
最新の投稿
- 2024.01.22相続全般不動産の相続で必要な登録免許税とは?計算方法や納付方法について解説
- 2023.09.17遺留分侵害請求相続人の具体的相続分と法定相続分・指定相続分の違いは?
- 2023.09.17相続全般遺産相続の相談先は?弁護士・税理士・司法書士・行政書士を徹底比較
- 2023.07.18相続手続き代行実印、銀行印、シャチハタ、三文判…相続で使えるハンコ(印鑑)は?
無料