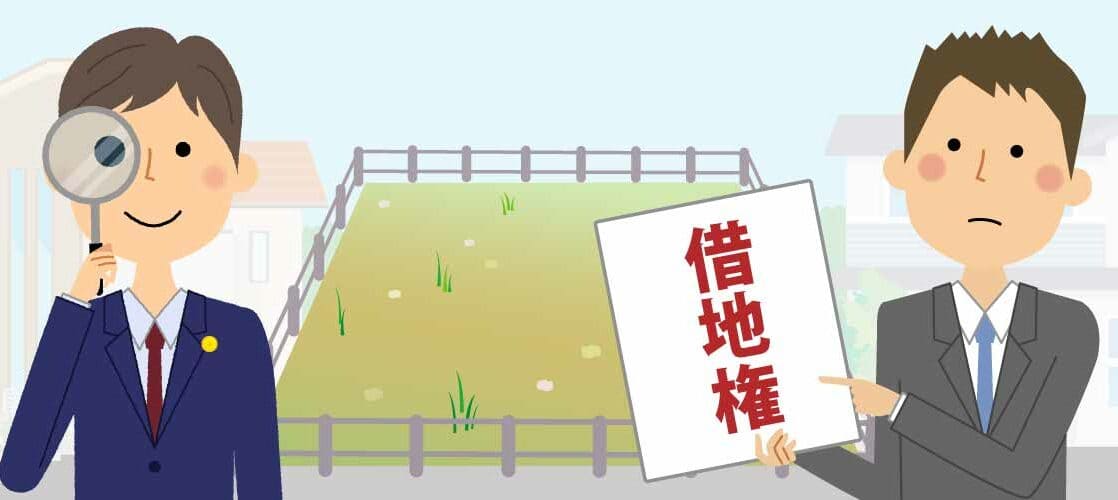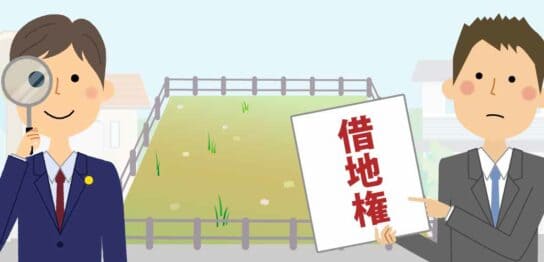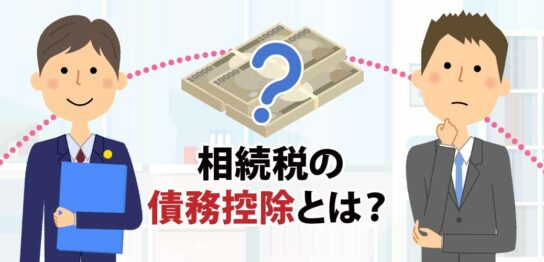- 借地権は相続の対象である
- 借地権は課税資産に含まれるので、相続税が発生する可能性がある
- 借地権の相続税の計算方法は、普通借地権か定期借地権かで異なる
【Cross Talk 】借地権を相続した場合、相続税の計算はどうなるの?
親が借地権という権利を持っていようなのですが、借地権は相続の対象になるのでしょうか?また、相続税が発生しないかも気になります。
借地権は土地を借りて自分が住むための建物を建てられる権利であり、相続の対象です。すなわち、借地権は課税資産と評価され、相続すると相続税が発生する場合があります。
借地権は相続の対象であり、相続税が発生する可能性があるのですね。借地権の相続税の計算についても教えてください!
親の遺産を相続する場合に、借地権という権利を相続する場合があります。 借地権は地主の土地を借りて、自分が住むための建物を建てられる権利ですが、借地権を相続すると相続税が発生する可能性があります。 そこで今回は、借地権を相続した場合の相続税の評価方法について解説いたします。
借地権を相続した場合の法律関係について

- 借地権は相続の対象になる
- 借地権は課税資産なので、相続税が発生する可能性がある
親が借地権という権利を持っているらしいのですが、相続の対象になるのでしょうか?
借地権は相続の対象です。借地権は課税資産と評価されるので、借地権を相続すると相続税が発生する可能性があります。
借地権とは
借地権とは、土地を所有する地主から土地を借りて、その土地のうえに自分が住むための建物を建てることができる権利です。例えば、自分の家を建てたいが土地がない場合に、知人の土地に借地権を設定して土地を借り、その土地に自分の家を建てて居住します。 上記の場合、借地上の建物は自分のものですが、土地は所有者である知人のものです。
なお,借地権は居住用の建物を建てる目的で土地を借りる場合の権利であり,借地借家法(旧借地法)に規定されている権利です。一方,同じように土地を借りる場合であっても,例えば駐車場として使うために他人の土地を借りる場合における土地を借りる権利のことは,借地権とは呼びません。
そして,現在の借地借家法における主な借地権の種類としては、普通借地権と定期借地権があります。 法律上、普通借地権は30年以上、定期借地権は50年以上といった長期間の契約期間である必要があります。 普通借地権は基本的には契約を更新すれば借地権を継続できるのに対し、定期借地権は基本的には期限が終われば土地を返還しなければなりません。なお,平成4年7月31日までの契約で設定された借地権は現在の借地借家法の前進である旧借地法における借地権となるため旧借地権,同年8月1日以降の契約で設定された借地権は現在の借地借家法における借地権となるため新借地権と呼ばれたりもします。
借地権と所有権の違い
借地権は所有権とはどのような違いがあるのでしょうか。 借地権は土地を借りて建物を建てることができる権利ですが、所有権は物(土地)を所有する権利です。土地の所有権を有していれば、土地を自由に利用することが可能ですし、抵当権などの担保を設定する、売却するなどの処分行為をする権利も持っています。 一方で借地権では、土地に建物を建てて利用することが可能ですが、その土地自体に対して抵当権などの担保を設定したり売却をしたりすることはできません。
借地権の種類
借地権には大きく次の3つの種類があります。- 普通借地権
- 旧借地権
- 一般定期借地権
- 堅固な建物は60年(合意があればその期間・ただし最低30年)
- 非堅固な建物は30年(合意があればその期間・ただし最低20年)
- 最低期間を下回った場合には合意がなかったとみなして堅固な建物60年・非堅固な建物の場合は30年となる
借地権は相続の対象になる
借地権は相続の対象になります。 相続の対象となる財産を相続財産といいます。相続財産の例として預貯金・不動産・有価証券・自動車などがありますが、借地権も相続財産であり、相続の対象となります。例えば、被相続人が生前に居住していた家が借地上にある場合、被相続人の所有する家だけでなく、家のために設定されている借地権も相続されます。 被相続人が亡くなって相続人が借地権を相続した場合、以降は相続人が借地権者になります。
借地権を相続するのに地主の許可は不要
通常は,借地権は特定の方が利用することを前提に設定されます。所有権者は契約にあたって借地権者となる方が適正に土地を利用してくれる方か見極めて契約をするので、借地権者が誰かは非常に重要です。そのため、借地権を譲渡する場合には、相続の場合と異なり所有権者である地主の承諾が必要なのが一般的です。一方で,借地権を相続するにあたって、所有権者である地主の許可は不要です。相続は,被相続人の地位をそのまま承継するものなので,法律上は相続人=被相続人と理解されるためです。 そのため,相続も所有権の移転であることには変わりないのですが、相続が発生したことを所有権者である地主に通知すればよく、承諾を得ることや譲渡承諾料の支払いは不要です。
相続人以外の方に借地権を遺贈する場合には地主の許可が必要
相続人以外の方に借地権を遺贈する場合には地主の許可が必要です。 相続人に遺贈をする場合は、相続と同様に考えることができますが、相続人以外の方への遺贈は、借地権の譲渡と同視できるためです。相続した借地権の売却には地主の許可が必要
相続した借地権を第三者に売却するには、地主の許可が必要です。 借地権を相続するのには地主の許可は不要ですが、相続人が借地権を売却して譲渡する場合には、新たに借地権となる人が適切な利用が期待できるか等を地主が検討できるように,地主の許可が必要となります。相続後に建物を建て替えることは可能か
借地権を相続してその場所に住むことになる場合、従来の建物では生活に不便で建物を建て替えることを検討することもあります。 この場合、借地権を設定した際に、立て替えについてどのような合意があったかによって、結論が異なります。 もし立て替えを制限する合意があった場合には、自由に立て替えをすることはできず、立て替えをするには地主の承諾が必要です。 もし承諾を得られない場合に、勝手に立て替えをした場合には契約を解除される可能性があるので注意が必要です。 承諾を得られない場合には、裁判所に許可を求める申立てによって、裁判所に許可をもらって立て替えをすることになります(借地借家法17条2項)。借地権も相続税の課税資産の対象となる
借地権は、相続税の課税資産の対象に含まれます。 課税資産とは、税金が課される対象になる資産のことです。相続税の課税資産としては預貯金・不動産・有価証券などがありますが、借地権も課税資産に含まれます。つまり、借地権を相続する場合は、相続税を納めなければならない可能性があるのです。 相続税が課されるか否か、課される場合の相続税の額を算定するには、まずは相続税の計算の基礎となる価格を計算する必要があります。
そこで、普通借地権と定期借地権について、相続税の計算の基礎となる価格の算出方法を次に解説いたします。
借地権の相続税の評価方法

- 相続税の評価方法は、普通借地権と定期借地権とで異なる
- 定期借地権のほうが計算式は複雑になる
親の借地権を相続することになりそうなのですが、相続税が心配です。借地権の相続の評価方法を教えてください。
相続税の評価方法は普通借地権と定期借地権で異なり、定期借地権の方が計算が複雑です。
普通借地権の評価方法
普通借地権の評価方法は、以下の計算式によります。普通借地権の価額 = 自用地の価額 × 借地権割合
ある土地について所有権以外の権利がなく、所有者が制約なしで自由に利用できる土地を、自用地といいます。 例えば、土地に借地権が設定されている場合は、所有者が自由に自分の土地を使えるわけではないので、自用地には該当しません。
自用地のおおよその価格を算出するには、一般に以下の2種類の計算式を用います。
・倍率地域の場合:固定資産税評価額 × 倍率
路線価とは、路線(道路)に面する標準的な宅地について、1平方メートル当たりの価額を表したものです。路線価を用いて土地の価格を計算する地域のことを、路線価地域といいます。
倍率地域とは、路線価が設定されていない地域です。倍率地域においては、土地の固定資産税評価額に一定の倍率をかけて価格を計算しますが、この計算方法を倍率方式といいます。 自用地の価格を計算するには、まずその土地が路線価地域にあるのか、倍率地域にあるのかを調べなければなりません。国税庁のホームページなどで確認するのが一般的です。
自用地の価額を算出して借地権割合をかけることで、普通借地権の価格を計算します。 借地権割合は地域ごとに規定されており、インターネットで路線価図を閲覧すれば、その地域の借地権割合を確認できます。
計算の例です。普通借地権が設定された土地の路線価が、1平方メートルあたり2万円であるとします。土地の地積が100平方メートルの場合、自用地としての土地の価格は200万円です。 その土地が存在する地域の借地権割合が60%の場合、200万円の60%なので、普通借地権の価格は120万円です。
借地権を相続するうえでの注意点

- 借地権を相続するうえでの注意点
借地権を相続する際に注意すべきことはありますか?
いくつか注意すべきことがあるので注意しましょう。
共有はトラブルに繋がる
借地権・建物を相続する場合に、共同相続人で共有とする場合があります。 この場合、共有者の一人のみしか建物を利用しない場合や、共有者の一人が売却をしたい場合、固定資産税や管理費用の負担、ほかの共有者の持分に相当する賃料の支払いなどでトラブルとなることがあります。 できるかぎり共有は避けるとともに、やむを得ず共有にする場合には、トラブルにならないように細かい条件をしっかり決めておくようにしましょう。地主との関係を維持する
地主との関係をきちんと維持するようにしましょう。 特に、借地権を設定して長い期間が経過している場合には、周辺の地価が大きく上がっているような場合もあります。相続をきっかけに地代の引き上げを要求されることもありますので、そのような場合には引き上げ額が相場と比べて適切かなどを調べるようにしましょう。相続放棄
借地権がついている建物を相続することになったものの、その建物を利用しない場合もあります。 相続をすることによって、地代の支払い・固定資産税や管理費用などの支払いが必要となります。 地主に借地を返還する場合には建物を解体する必要があり、解体費用がかかる場合があります。 このような費用を支払いたくない場合には、相続放棄をすることも検討しましょう。 相続放棄をすれば相続人とならないため、上述した費用を負担する必要はありません。 もっとも、相続放棄をすると他の遺産も相続することができなくなるので、注意が必要です。借地の固定資産税の支払い義務
借地について相続をきっかけに地主から固定資産税の負担を求められることがあります。 固定資産税は土地の所有者である地主に対して課せられる税金で、借地権者は所有者ではなく借りているに過ぎず、固定資産税の支払い義務はありません。 通常地代の決定には、管理費用や固定資産税を考慮されるので、地主から固定資産税の支払いを依頼された場合には事実上二重に負担させられる可能性があります。 もっとも、固定資産税は土地の価額に税率を乗じて計算されるところ、土地の価額が上がっているような場合には、固定資産税の負担も借地権設定契約当初よりも増えていることがあります。 どのような事情で地主が固定資産税の支払いを求めているのかを確認するようにしましょう。借地権の中途解約
借地権は一度設定されると基本的に設定された期間は存続することになりますが,当事者の合意により中途解約をすることはできます。 設定される借地権の存続期間が一般的に長期間になることから,その期間中に契約を終了させたい様々な事情が生じる可能性があります。 そのため、通常は中途解約に関する事項を借地権を設定する契約の中で定めています。 相続をする際には中途解約に関する事項まで把握していない可能性があるので、相続した場合にはどのような条件のもとに借地権が中途解約されるかは、しっかり確認しておくようにしましょう。まとめ
借地権は相続の対象であり、課税資産と評価されるので、相続によって相続税が発生する場合があります。 相続税の評価方法は、普通借地権か定期借地権かによって計算式が異なるので注意しましょう。 借地権の評価方法を正確に計算したい場合は、相続に詳しい専門家に相続することをおすすめいたします。

この記事の監修者
最新の投稿
- 2024.01.22遺産分割協議法定相続人が配偶者・兄弟姉妹の場合は争いになりやすい?実例と対策について解説
- 2023.11.23相続税申告・対策借地権を相続した場合の相続税の評価の方法について
- 2023.11.19遺産分割協議相続で揉めてしまったときには裁判(訴訟)?紛争別の解決
- 2023.10.22相続全般別居中の配偶者が亡くなった場合、相続や遺留分はどうなる?弁護士が解説
無料