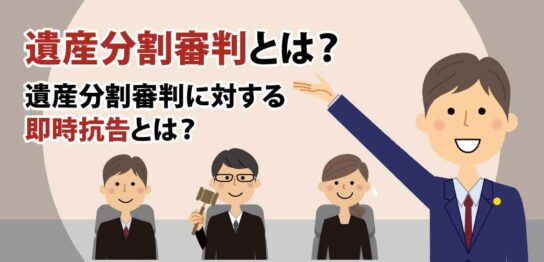- 争いの解決方法は裁判(訴訟)だけではない
- 裁判(訴訟)以外の解決手段として、当事者による話し合い・調停・審判がある
- 相続争いごとにどのような解決の道筋をたどるかを確認
【Cross Talk 】相続に関する争いはどのようにまとめればいいですか?
先日父が亡くなり、母・私(長男)・妹(長女)で相続をすることになりました。遺産分割の話し合いをしているのですが妹がどうしても納得してくれません。このような場合には裁判(訴訟)しか解決方法はないのでしょうか。
裁判(訴訟)の他にも調停や審判などいくつかの解決方法があります。
詳しく教えてください。
相続について争いになってしまった場合には、裁判(訴訟)しかないのでしょうか。 相続については家族に関する問題ということもあって、紛争になった場合の解決方法として、調停・審判といった解決方法があります。相続に関する争いといっても、その争いを解決するために何を争わなければならないかによって解決手段も異なるので、相続の何で争っているかによってどのような解決方法があるかと一緒に確認しましょう。
相続にまつわる争いの解決方法について

- 相続争いを話し合う際のコツ
- 相続争いの紛争解決手段には調停・審判・裁判(訴訟)がある
相続争いの紛争解決手段にはどのようなものがありますか?
調停や審判などの裁判(訴訟)以外の手段も知っておきましょう。
相続において当事者の話し合いが上手くいかなくなった場合にはどのような解決手段があるのでしょうか。
弁護士を通しての話し合い
当事者同士の話し合いが上手くいかない場合は、法的な手段を考えるかと思います。 ただ、その場合に一度検討していただきたいのが、弁護士に依頼をして交渉をするという方法です。 相続争いが激しくなってくると、財産的な側面で既に折り合いがついていても、感情的な側面で折り合いがつかず、話し合いが上手くいかない場合があります。感情的な対立を抱えたまま、面と向かって交渉を続けても、感情的な対立が深まり解決には向かいませんので、そのような場合には弁護士に代理人となってもらって交渉を進めることで、解決に向かって話し合いを進めていくことができます。
調停
当事者同士で話し合いをしても解決が難しい場合には、法的な手続きによって紛争解決せざるを得ません。 裁判所で行う手続きに関しては、裁判(訴訟)以外にもいくつかあり、調停はそのうちの一つです。調停の概要
調停は裁判所で行う手続きの一つで、裁判官と調停委員から構成される調停委員会が、双方の意見をすり合わせながら話し合いによる合意を目指す紛争解決方法です。手続は裁判所でおこなわれますが、手続中は別々に意見を聞かれるので、面と向かって交渉をする、ということはありません。 なお、遺産分割事件についての法的手続きを採る場合、法律上、原則として調停手続を最初に行う必要があります。
調停の流れ
調停は次のような流れで進みます。- 当事者の一人が申立て
- 他の相続人に呼出状が送達される
- 第一回期日が開催
- 話し合いがまとまらなければ第二回・第三回と続く
- 話し合いがまとまれば調停成立・まとまらなければ調停不成立→審判へ移行
審判
調停で解決しない場合には審判が利用されることがあります。審判の概要
審判は、調停と同じく裁判所でおこなう裁判手続きの一種ですが、当事者の主張に裁判所が拘束されず、裁判所が法律を踏まええ判断するものです。 調停は裁判官のほかに民間の専門家が調停委員として紛争解決に加わりますが、審判は裁判官だけがおこないます。 当事者双方が裁判官のいる部屋に呼ばれて手続きをおこないますので、顔を合わせながら手続きをおこないます。 調停の場合には合意ができなければ効力が発生しませんが、審判の場合には不服申立ての手続きをとらなければ、審判の内容に従わなければなりません。審判の流れ
- 調停不成立で審判に移行
- 裁判所から呼出状が届く
- 第一回期日
- 裁判所が判断できるまで第二回・第三回と続く
- 裁判所によって審判が下される
- 不服があれば即時抗告が必要、即時抗告をしなければ審判の翌日から2週間で審判が確定
裁判
法的な紛争解決手段として、最もイメージできるのは裁判(訴訟)ではないでしょうか。裁判の概要
裁判(訴訟)は、公開の法廷で、裁判所に判決をしてもらって紛争解決をする手続きになります。 裁判の最中に和解が試みられることもあり、和解をした場合にはその内容での紛争解決となります。 和解に至らない場合には最終的には裁判所が出す判決に従うことになります。裁判の流れ
裁判は次の流れで進みます。- 訴状の提出
- 訴状の送達および期日の呼び出し
- 第一回口頭弁論期日
- 裁判所が判断できるまで第二回・第三回と続く
- 途中で和解が試みられることもあり和解期日が設けられる
- 判決
- 不服であれば2週間以内に控訴・上告をおこなう。2週間以内に控訴・上告がなければ判決が確定
調停・審判・裁判の違い
調停・審判・裁判は、いずれも裁判所での手続きであるという点で共通しています。 しかし、調停が当事者の合意がなければ成立しないものであるのに対して、審判と裁判は裁判所が一方的に審判や判決を下すものになります。また、手続きの公開可否については、裁判が原則として公開される一方、調停・審判は非公開でおこなわれます。 家族に関する遺産分割などのデリケートな問題は、できる限り非公開でおこなわれるべきと考えられているからです。そのため、遺産分割の問題は最初に調停・審判でおこなわれることとなっています。
相続の争いごとに解決方法を確認

- 相続の争いの内容ごとに解決方法を確認する
- 必ず調停から審判になるというわけではない
私の場合、遺産分割なので、調停をしてから審判ということになりますね。相続に関する争いはすべて調停をして、それでもまとまらなかったら審判なのでしょうか。
すべてそうであるとはいえません。相続に関する争いごとに、どのような解決方法を利用するか見てみましょう。
以上のような相続争いの解決方法があるのですが、争いの内容によって利用する手続きが異なります。 相続争いの内容ごとに確認しましょう。
遺産分割が上手くいかない場合|遺産分割調停・審判
遺産分割が共同相続人同士の協議では調わない場合には、遺産分割調停・遺産分割審判が利用されます。 まず遺産分割調停をおこない、調停が成立しない場合に遺産分割審判がおこなわれます。 当事者がどのような遺産を取得するかの意見が調わない場合や、特別受益・寄与分の額に争いがあり、遺産分割協議では合意に至らないような場合に利用が考えられます。遺言書は無効であると主張したい|遺言無効確認の訴え
遺言書が無効であると確認するためには、遺言無効確認の訴えを起こすことになります。 問題となっている遺言書が無効である場合、他に遺言書がなければ遺産分割をおこなうことになります。 遺言書を作成した当時は既に認知症であり遺言能力がなかった、作成した自筆証書遺言書は、法律が定める様式に反している、といった点を争う場合に利用が検討されます。遺産に含まれるかどうかを争っている|遺産確認の訴え
ある財産が遺産に含まれるかどうかを争う場合には、遺産確認の訴えを提起します。 遺産分割の前提として、遺産になる財産を確定する必要があります。例えば、相続人の一人の銀行預金について、その口座に預けられたお金の出どころが被相続人の財産であるような、いわゆる名義預金のような場合で利用されます。
相続人名義の口座になっているものの、出どころが被相続人であり、遺産として扱うべき場合には、まず遺産確認で当該口座の預金が遺産である旨の確定を求めて、遺産確認の訴えを起こすことが考えられます。 上記の例ですと、遺産確認の訴えの結果、名義預金であり被相続人の遺産であるという確認判決が得られれば、その認定を前提として、相続人で遺産分割をおこないます。相続人の確定をしたい|相続人の地位不存在確認の訴え
相続人の確定をしたいときに、相続人の地位不存在確認の訴えを提起することがあります。 例えば、ある相続人が、被相続人を強迫して遺言書を作成させたとします。 この場合、遺言書は無効となるのですが、さらに強迫して遺言書を作成させた相続人に関しては相続欠格となります(民法891条4号)。 民法891条各号にあたる場合、相続人になることはできません。ですが、当事者がどうしても相続人として相続させろと主張して譲らない場合には、相続人の地位不存在確認の訴えを提起して、相続人ではないと確認する判決をもらって争いを解決することが考えられます。遺留分を侵害された|遺留分侵害額の請求調停・遺留分侵害額請求訴訟
遺留分を侵害された場合には、遺留分侵害額請求をおこないます。 まずは交渉をするのですが、交渉でも支払わない場合には、遺留分侵害額請求調停・遺留分侵害請求訴訟をおこないます。 遺留分については金銭の請求なので、審判ではなく訴訟(裁判)となります。遺産分割が無効であると主張したい|遺産分割協議無効確認訴訟
遺産分割協議を無効であると主張する場合、遺産分割協議無効確認訴訟をおこないます。 例えば、遺産として多額の株式があったのですが、当事者が証券会社に口座があるのを見逃して遺産分割をしたとします。あとから見つかった株式口座が遺産分割の金額全体を考えるとあまりにも多額で、もし株式口座が遺産分割のときに発見されていれば、従前の遺産分割のような交渉をしなかったといえる場合があります。 このような場合、遺産分割協議は錯誤で取り消すことができますが(民法95条1項)、当事者間でその遺産分割協議を取り消すことの合意ができない場合は、遺産分割協議無効確認の訴えを提起することが考えられます。 遺産分割協議無効確認の訴えが認められた場合、改めて遺産分割協議をおこなうこととなります。使い込んだ遺産を返して欲しい|不当利得返還請求訴訟
相続人の一人が遺産を使い込んでいたような場合には、その相続人に対して他の相続人が不当利得返還請求をおこなうことになります(民法703条)。 その相続人が応じない場合には、不当利得返還請求訴訟を起こすことになります。相続の争いを長引かせないためのコツ

- 譲歩するラインを決める
- 弁護士に早めに相談・依頼する
相続の争いを長引かせないためにはどのようなコツがありますか?
譲歩するラインを決めることと、当事者の感情的な対立が激しい場合には、早めに弁護士に相談して依頼し、当事者で直接やり取りをせずに交渉をすすめるのも効果的です。
相続の争いを長引かせないためのコツとして、次の2つを知っておいてください。
譲歩するラインを決める
一つ目は、 譲歩をするラインを決めることです。 例えば、遺産分割調停・審判では、ありとあらゆることで対立してしまうと、どのように折り合いをつければよいか、調停委員・裁判官が判断できず、当事者が納得いく結論をうまく導き出せないことになります。 遺産分割で、何を相続したいのか、何についてなら譲歩をしてよいのかのラインを定めて、交渉をするようにしましょう。 譲ってよいもの・譲れないものがハッキリすると、なんとなく争っている状態から、何について争っていて、どのように考えるべきか当事者でも考えやすくなります。
なるべく早い段階から弁護士に相談・依頼する
相続などに関しては、単なる請求権の問題というよりは、長年の家族に関する事情が相まって感情的な対立が鋭くなってしまい、調整が難しくなっている場合があります。感情的な対立が鋭くなり険悪な雰囲気のまま当事者が顔を合わせたり、電話等で直接話したりすると、さらに関係が悪化し、交渉がまとまらず、かえって争いが長引く原因になりかねません。 このような場合には、弁護士に相談・依頼すれば、直接顔をあわせるわけではなく弁護士が緩衝材(クッション)のような役割を果たして、裁判・調停・審判等を利用しなくとも交渉で終わることもあります。
また、相手が無理な主張をしているような場合では、相手も弁護士に相談する・弁護士に依頼することによって、適切な主張に路線を変更してくれる可能性もあります。 早めに弁護士に相談・依頼してみてください。まとめ
このページでは、相続に関する争いが生じた場合の紛争解決方法についてお伝えしました。 相続問題は、金銭的な争いだけではなく、感情的な対立も生じますので、争いになった際は上手に解決する必要があります。 解決方法には裁判(訴訟)以外にも多数あることを知っていただいたうえで、上手な解決方法があるのか弁護士に相談してみましょう。

この記事の監修者
最新の投稿
- 2024.01.22遺産分割協議法定相続人が配偶者・兄弟姉妹の場合は争いになりやすい?実例と対策について解説
- 2023.11.23相続税申告・対策借地権を相続した場合の相続税の評価の方法について
- 2023.11.19遺産分割協議相続で揉めてしまったときには裁判(訴訟)?紛争別の解決
- 2023.10.22相続全般別居中の配偶者が亡くなった場合、相続や遺留分はどうなる?弁護士が解説
無料