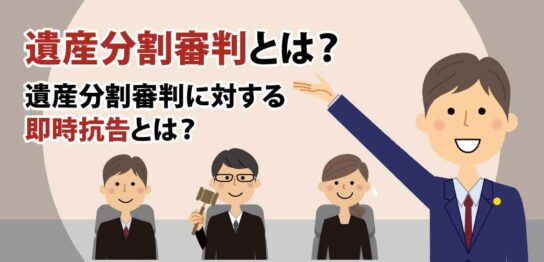- 遺産分割は、被相続人の遺産を各相続人に分ける行為
- 遺留分は特定の親族に認められた遺産の最低限の取り分。遺留分を侵害された際には遺留分侵害額請求ができる
- 遺産分割協議で相続人全員が合意している場合には、遺留分を侵害した内容でも問題にはならない
【Cross Talk 】遺産分割・遺留分とは?
そもそも遺産分割・遺留分とは一体でしょうか?
被相続人が亡くなった(相続が開始した)ことをきっかけに、被相続人の遺産を各相続人に分ける行為を遺産分割と言います。遺留分は特定の親族に認められた遺産の最低限の取り分を指します。
身近な方が亡くなった際「そもそも遺産分割とは何か」「遺留分があると聞いたがどうしたら良いか」と戸惑われる方は少なくありません。 遺産分割は被相続人の遺産を各相続人に分ける行為です。遺産分割協議には、判断能力が不十分な方(認知症など)には後見人を選任する、相続人全員が同意しなければならないといった決まりがあります。遺留分は特定の親族に認められている遺産のうち最低限得られる取り分を指します。 今回は遺産分割の概要や流れ・方法、遺留分について解説していきます。
遺産分割とは

- 基本的に遺言書があるときには遺言書通りに、遺言書がない場合には遺産分割協議で内容を決定する
- 遺産分割の方法には現物分割・換価分割・代償分割・共有分割の4種類がある
遺産分割はどのような流れで行うのでしょうか?
まずは、遺言書の有無を確認しましょう。遺言書があるときには遺言書通りに遺産を分けます。遺言書がない場合には相続人全員が話し合い相続の割合や方法を決める遺産分割を行うことになります。
遺産分割とは
相続が開始する(被相続人が亡くなる)と被相続人の財産を相続人で分ける必要が出てきます。相続人全員で遺産を分けることを「遺産分割」と言います。 民法906条では、遺産分割に関して以下のような規定があります。遺産分割の種類
基本的に遺言書がある場合には遺言書の内容に沿って遺産を分けていきます。遺言書がない場合には遺産分割を行う必要があります。相続人全員が話し合い、合意した内容で遺産を分割します。なお遺産分割の方法には、遺産を現物のまま分ける現物分割、売却した代金を分ける換価分割、相続人のうち1人が代表して相続し他の相続人には金銭または相応の遺産を譲る代償分割、共有名義にする共有分割があります。
不動産・貴金属など現物の遺産を分割する際には遺言書または遺産分割協議によって、上記の4つの方法からいずれかを選択します。遺留分とは

- 遺留分と遺族に定められた最低限の取り分を指す
- 遺留分を侵害された相続人は遺留分侵害額請求ができる
遺留分とは誰に対して認められているのでしょうか?
遺留分の権利を持つ方は、被相続人の配偶者、子ども(子どもが亡くなっている場合は孫)、父母(父母が亡くなっている場合は祖父母)です。
遺留分とは
遺留分とは被相続人の親族に定められた最低限の取り分を指します。 被相続人の配偶者、子ども(子どもが亡くなっている場合は孫)、父母(父母が亡くなっている場合は祖父母)に遺留分の権利があります。兄弟姉妹も被相続人の配偶者や子どもなどと同様に法定相続人(民法で定められた相続人)ですが、遺留分はありません。
民法では、遺留分を以下の通り定めています。| 遺留分権利者 | 遺留分の割合 |
|---|---|
| 相続人が直系尊属(父母など)のみ | 遺留分算定の基礎となる財産の1/3 | 配偶者や子どもなど上記以外 | 遺留分算定の基礎となる財産の1/2 |
遺留分侵害額請求とは
遺言書等の内容が遺留分を侵害しており相続人の間の話し合いでも解決できない際には、家庭裁判所に遺留分侵害額の請求調停を申立てることができます。遺留分侵害額請求の権利は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年、または相続開始から10年を経過したときに時効によって消滅してしまいます。 期間内に、遺留分侵害額請求を行う意思表示及び調停申立てを行い、調停委員や裁判官を交えて解決に向けて話し合いを行います。
調停でも意見がまとまらない場合には、訴訟を起こす流れとなります。 遺留分侵害額請求についての詳しい内容はこちら「遺留分侵害額(減殺)請求権とは?行使方法は?時効は?」の記事をご確認ください。遺産分割と遺留分の関係

- 遺留分は生前贈与や相続務を考慮した一定の式で算定する
- 遺産分割が不平等な分配割合でも相続人全員の合意が有れば遺産分割協議は成立する
遺産分割で遺留分はどう取り扱ったら良いのでしょうか?
遺留分を侵害しないように配慮する必要がありますが、相続人全員が合意しているときには不平等な内容でも問題ありません。ただ、協議後は遺産分割協議書を必ず作成しておきましょう。
遺留分を侵害している場合の具体例
遺留分は生前贈与や相続債務を考慮した一定の計算式が存在します。 配偶者が子どもの遺留分を侵害している以下の場合で遺留分の額を計算してみましょう。相続財産の価額:5,000万円
遺産の分割内容:配偶者が4,000万円、子どもが1,000万円
相続開始から1年前までの生前贈与の価額:無し
相続債務:無し
遺留分の算定の基礎となる遺産の価額は「相続開始時の財産の価額(遺贈を含む) +被相続人が生前に贈与した財産の価額―相続債務」です。 「被相続人が生前に贈与した価額」に算入される贈与は、基本的に相続開始前の1年のものに限定されますが、相続人に対して行われた場合は、相続開始前の10年になされた婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本としてなされた贈与も含まれます。
上記の例でいうと、遺留分の算定の基礎となる遺産の価額は5,000万円となります。
遺留分の額は、「遺留分算定の基礎となる財産の価額×個別的遺留分の割合」で算定します。 民法1042条で規定されている遺留分は、遺産全体に対する割合(総体的遺留分)であり遺留分の権利者が複数いる場合には、総体的遺留分を法定相続分の割合にしたがって配分した「個別的遺留分」で計算します。
配偶者と子どもの2人が相続人である場合には、総体的遺留分は1/2、配偶者の個別的遺留分は1/4(1/2×1/2)、子どもの個別的遺留分は1/4(1/2×1/2)です。よって、子どもの遺留分は5,000万円×1/4=1250万円となります。
遺産分割協議で不平等な分配になっても相続人全員が合意していれば問題にならない
遺産分割協議で1人または複数の相続人にとって不平等な分配になった場合でも、相続人全員が合意している際には遺産分割協議は成立します。上記のように子供の遺留分を侵害する遺産分割を行う場合でも、子どもがその分割内容に同意しているときには遺産分割ができます。 ただ、後のトラブル回避と手続きのために協議後に遺産分割協議書を作成しておくことが必須となります。
なお、被相続人が生きているうちに「遺留分を放棄したい」という推定相続人がいる場合、家庭裁判所に「遺留分放棄の許可」を申請する事も可能です。
まとめ
このページでは遺産分割と遺留分について解説してきました。 遺留分侵害額請求の権利は相続開始(もしくは遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知ったとき)から1年、または相続開始から10年を経過したときに消滅してしまいますので注意しましょう。 遺産分割や遺留分で疑問がある方やトラブルを避けたい方、トラブルが起きてしまった際には相続に詳しい弁護士に相談する事をおすすめします。

この記事の監修者
最新の投稿
- 2024.03.22相続放棄・限定承認遺留分放棄とは?相続放棄との違いやメリット、撤回の可否を解説!
- 2023.11.06相続全般「死んだら財産をあげる」相続における口約束はトラブルのもと!事例をもとに解決方法を解説
- 2023.07.18遺言書作成・執行遺言書を紛失した場合にはどう対応すればいいか?
- 2023.06.30相続税申告・対策死亡退職金は相続税の課税対象になる?
無料