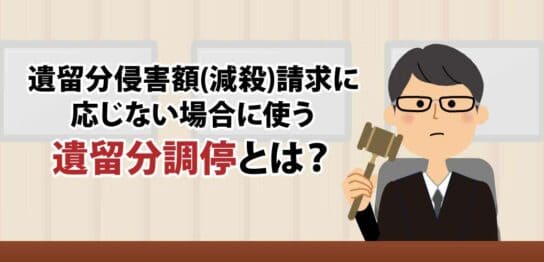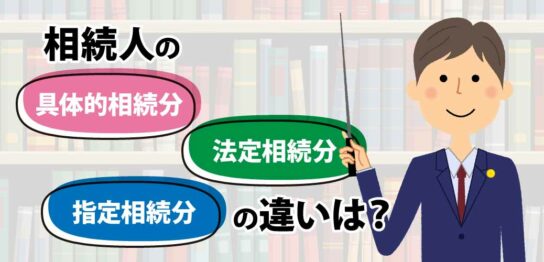- 兄弟が相続人になる場合
- 兄弟が相続人になる場合の注意点
- 兄弟には遺留分はない
【Cross Talk 】子どもがいないのですが兄弟が相続人になるのでしょうか
今から自分が亡くなったときの相続について準備をしようと思っています。私には妻がいるのですが子どもがおらず、両親・祖父母はすでに他界しています。兄弟がいるのですがあまり連絡をとっていません。妻が困らないようにしておきたいと思ったときにはどうすべきでしょうか。
その場合ですとご兄弟様が相続人になります。兄弟姉妹には遺留分はないので、奥様に全ての遺産を相続させることも可能ですよ。
そうなんですね!詳しく相談にのってください。
亡くなったあとに誰が相続人になるかについては、法律(民法)で規定されています。兄弟姉妹は子ども・直系尊属がいない場合に相続をすることが規定されています。 また、相続人には遺留分があるのですが、兄弟姉妹には遺留分は認められていません。兄弟姉妹が相続人になるケースを詳しく見るとともに、遺留分がないことに留意した相続対策などについて確認しましょう。
兄弟姉妹が相続人になる場合の相続分・遺留分

- 兄弟姉妹が相続人になるケース
- 兄弟姉妹には遺留分がない
そもそも兄弟姉妹が相続人になるのはどのような場合ですか?
代襲相続人を含む子ども・直系尊属がいない場合です。
兄弟姉妹が相続人になる場合の法律関係をしっかり確認しましょう。
兄弟姉妹が相続人になる場合
誰が相続人になるかについては、民法887条、889条、890条で次のように規定されています。 まず、相続人に子どもがいる場合には子どもが相続人となります(民法887条1項)。民法887条の規定によって相続人となる人がいない場合には、被相続人の直系尊属が(民法889条1項1号)、直系尊属がいない場合には、兄弟姉妹が相続人となることが規定されています(民法889条1項1号)。 直系尊属とは、血縁関係が直系である、自分より上の世代の血族で、親・祖父母などの上の世代のことです。 大雑把に言うと、子どもがおらず、親・祖父母もいない場合に兄弟姉妹は相続人になる、ということになります。
子どもがいないといっても、子どもに孫がいる場合には代襲相続が発生するので(民法887条2項)、代襲相続人も含めて検討することになります。 子どもがいる場合の相続を第1順位の相続、直系尊属が相続する場合の相続を第2順位の相続、兄弟姉妹が相続をする場合の相続を第3順位の相続と呼んでいます。 配偶者は常に相続人となり、上記の相続人と共同相続をすることになります(民法890条)。
兄弟姉妹が相続人になる場合の相続分
兄弟姉妹が相続人になる場合の法定相続分は配偶者の有無によって異なります。 配偶者がいない場合には、兄弟姉妹の頭数で均等に相続をします これに対して、配偶者がいる場合には、配偶者の相続分は3/4・兄弟姉妹の相続分は1/4となり、兄弟姉妹が複数いる場合には1/4の相続分を頭数で均等に相続します。 兄弟姉妹が3人いるときは、配偶者がいない場合には1/3ずつを、配偶者がいる場合には(1/4×1/3)=1/12ずつの相続分となります。兄弟姉妹には遺留分は認められていない
相続人には、相続において最低限主張できる権利である遺留分が認められています。 ただし、遺留分を規定する民法1042条1項本文において、「兄弟姉妹以外の相続人は、」とされており、兄弟姉妹は明確に除外されています。 そのため、兄弟姉妹には遺留分は認められていません。兄弟姉妹が相続人になる場合の注意点

- 兄弟姉妹に相続をさせたくない場合には遺言書をしておく
- 配偶者がいる場合にはトラブルになるようなことがあるので遺言書をのこしておく
兄弟姉妹が相続人になる場合に備えての注意点はありますか?
配偶者と兄弟姉妹が共同相続をするような場合、ほとんど交流もないような場合もあり、相続で揉めてしまうこともあります。どのような希望があるにせよ遺言書を残しておくことが望ましいといえるでしょう。
兄弟姉妹が相続人になる場合の相続についてはどのような注意が必要でしょうか。
兄弟姉妹に相続させたくない場合には遺言書を作成する
兄弟姉妹が相続人である場合、遺留分が認められていないので、他の相続人に遺贈や生前贈与をしても、遺留分侵害額請求などの主張ができません。 そのため、兄弟姉妹の中でどうしても相続をさせたくない、という方がいる場合には、遺言書を残しておくことでその希望がかないます。 特定の兄弟姉妹には相続させたくないような場合や、特定の兄弟姉妹にのみ相続をさせたいという希望があるのであれば、遺言書を残しておきましょう。配偶者がいる場合には遺言書をしておくのが良い
特に配偶者がいて、子どもがいないという場合には遺言書を残しておくべきです。 配偶者がいる場合の兄弟姉妹の相続分は1/4で、兄弟姉妹が複数いる場合には頭数で割るので、一人一人の相続分は多くはないです。しかし、配偶者と兄弟姉妹は、頻繁に交流がないことも多く、一人当たりの相続分も少ないというのであれば、相続をする当事者としては「これくらいの額だし親しい仲でもないので貰えるものは貰っておこう」と考えることがあります。 兄弟姉妹が、不動産の持分や、中古の自動車をもらいたいとは思わない場合、遺産として現預金を欲しいと主張することも多く、すぐに支払いができない場合にはトラブルになり、自宅を売却しなければならないという結論になることも否定できません。
配偶者の生活を守りたい、というのであれば、遺言書を残して確実に配偶者が生活に困らないような準備をしておくことが望ましいでしょう。まとめ
このページでは、兄弟姉妹が相続人になる場合や遺留分についてお伝えしました。 兄弟姉妹は子どもや直系尊属がいない場合に相続人となるものとされていますが、一方で遺留分は法律で認められていません。 兄弟姉妹が相続人になる場合、特に配偶者がいても子どもがいない場合には、遺言書を作成するなどの準備を念入りに進めておくべきといえます。 どのような対策がベストかは、遺産の内容や相続人によって異なりますので、弁護士にご相談ください。

この記事の監修者
最新の投稿
- 2023.08.11相続全般自殺で損害が生じた場合は相続人が損害賠償義務を負う?自殺の際の相続手続きについても解説
- 2023.08.11相続全般個人事業主が亡くなった場合の相続手続きはどうなるの?
- 2023.07.18相続全般息子の配偶者にも遺産をあげたい場合の対応方法を弁護士が解説
- 2023.07.18相続全般被相続人が外国人だったら違いはあるの?相続人が外国人だったら?
無料