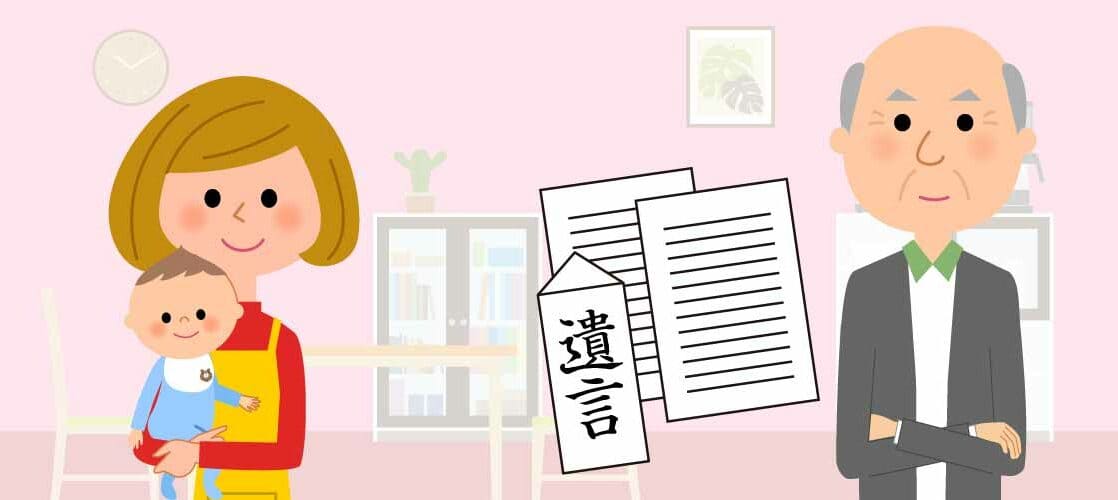- 内縁の妻、相続・寄与分の請求・特別寄与料の請求はできない
- 特別縁故者であれば遺産を受け取ることができるが要件が厳しいうえ時間がかかる
- 内縁の妻に遺産を残す場合には遺言書で遺贈をする
【Cross Talk 】内縁の妻に多少遺産を残してあげたい
私の相続についてご相談があります。妻に先立たれて子どもが独立したあとに、内縁の妻ができました。高齢にはなるので何かあったときに、妻が露頭に迷わないようにしてあげたいのですが、何をしておくべきでしょうか。
内縁ということであれば相続権がないので、遺言書を残しておくべきです。
詳しく教えてください。
事実上婚姻関係にあるにもかかわらず、婚姻の届け出を行っていない夫婦の関係を内縁と呼びます。内縁の妻は、相続にいう配偶者にはあたらず、相続権がないのが判例の立場です。相続人や親族に認められる制度の適用もなく、特別縁故者にあたれば遺産を受け取ることも可能ですが、要件が厳しく時間もかかります。そのため遺言書を残して遺贈をするのが現実的です。 このページでは、内縁の妻に遺産を残す方法についてお伝えいたします。
内縁の妻が遺産を得ることができる制度

- 内縁の妻には、相続権・寄与分・特別寄与料認められず、特別縁故者になることができるのみである
- 内縁の妻にスムーズに遺産を譲り渡すには遺言書を残しておくのが現実的
内縁の妻に遺産を譲り渡す方法にはどのようなものがありますか?
何も対策をしなければ特別縁故者に該当しなければ遺産は譲り受けられません。遺言書をしておくのが一番現実的です。
内縁の妻が遺産を受け継ぐことができる可能性について検討しましょう。
内縁の妻は配偶者ではないので相続権はない
まず、内縁の妻には相続権はありません。 内縁とは、事実上婚姻関係にありながらも、法律上の届け出をしていない関係のことをいいます。 民法は,内縁であっても、なるべく婚姻に関する規定(扶助義務・婚姻費用の分担など)を類推適用しようとしています。 しかし、相続に関しては、画一的な処理をする観点から、判例でも相続権を認めていません。寄与分は相続人に認められるもので内縁の妻には認められない
寄与分とは、相続人の遺産の増加や維持をした相続人がいる場合に、相続において有利に扱う制度です(民法904条の2)。 寄与分が認められるのは相続人に対してですので、内縁の配偶者に寄与分は認められません。特別寄与料は親族に認められるものなので内縁の妻には認められない
特別寄与料とは、被相続人の親族の中に、被相続人の遺産の増加・維持に貢献したと認められる人がいる場合に認められる制度です(民法1050条)。 この制度にもとづく請求が認められるには、親族である必要があり、内縁の妻には認められません。内縁の妻が遺産を受け取ることができるのは特別縁故者になった場合だけ
最後に、内縁の妻が遺産を受け取ることができる場合を検討すると、特別縁故者に該当し、遺産の配当を受けることができる場合があります。 特別縁故者とは、相続人がいない場合に、被相続人と生計を同じくしていたり、被相続人の療養看護に努めたなど、特別な関係があった場合に、家庭裁判所に請求をして遺産を与えてもらう制度です(民法958条の3)。相続人が居ない場合には、利害関係人が家庭裁判所に申立てをして、相続財産管理人主導のもと、相続人不存在の場合の手続き(民法951条以下)を行うことになります。 この手続きが終わり、相続人の不存在が確定した場合に、特別縁故者への遺産の配分が行われます。 内縁の妻は、家計を同一にしていたり、被相続人の療養看護をしていると認められる可能性が高いのです。 しかし、そもそも相続人が一人でもいれば特別縁故者として遺産を受け取ることができません。 また、仮に特別縁故者として遺産を受け取ることができる場合でも、実際に遺産を手にすることができるのは、被相続人が亡くなってから相当期間経過後になるので、スムーズに遺産を受け継がせることができません。
遺言(遺贈)であれば内縁の妻にも遺産をのこすことができる
遺言書で内縁の妻に遺産を与える遺贈をすれば、内縁の妻でも遺産を受け取ることができます。 そのため、内縁の妻に遺産をスムーズに渡したいという希望があるのであれば、遺言書をのこしておくことが不可欠であるといえるでしょう。遺言で内縁の妻に遺贈をする場合の注意点

- 遺留分を侵害すると内縁の妻が遺留分侵害額請求を受けることになる
- 遺族と交渉をすることになる負担をかける可能性があるので遺言執行者をつけるのが望ましい
なるほど、遺言書をのこしておこうと思いますが、遺言書を作成するにあたって何か注意点はありますか?
遺留分の規定など、内縁の妻に遺言書を残す場合の注意点について確認しましょう。
内縁の妻に遺言書で遺贈をする場合の注意点を確認しましょう。
相続人がいる場合には遺留分に注意する
まず、相続人がいる場合には遺留分に注意しましょう。 遺留分とは、相続人が最低限の遺産を相続できる権利のことをいいます。 兄弟姉妹以外の相続人には、相続分の1/2(直系尊属のみが相続人である場合には1/3)が遺留分として認められており、この分を相続できない場合は、遺贈を受けた内縁の妻が遺留分侵害額請求を受ける可能性があります(民法1042条・1046条)。遺留分を侵害しないようにしたり、遺留分侵害額請求を受けてもきちんと支払いをすることができるようにしておくべきといえます。 遺留分については「遺留分とは?相続分との違いは?遺留分は親や孫にも認められる?」で詳しく説明していますので参考にしてください。
遺言が無効にならないように注意する
次に、遺言書の内容が無効にならないように注意しましょう。 特に、自分で作成を行う自筆証書遺言や秘密証書遺言については、内容を誤ると遺言が無効であると判断される可能性があります。 公証人により作成されるため信頼が高く、遺言書の検認が不要となる、公正証書遺言の作成が望ましいといえます。内縁の妻と遺族との交渉が発生する
単に遺言書を作成すると、相続人がいる場合、内縁の妻は相続人に対して遺産の引き渡しについて交渉をする必要があるケースがあります。 これによってトラブルとならないように、遺言執行者をつけておくことも検討しましょう。まとめ
このページでは、内縁の妻が遺産を取得するための方法についてお伝えしました。 何もしなければ、特別縁故者に該当する場合にしか遺産を手に入れることができません。 できる限り遺言書をしておくことが望ましいので、不安なことがあれば弁護士にご相談ください。

この記事の監修者
最新の投稿
- 2024.03.22相続放棄・限定承認遺留分放棄とは?相続放棄との違いやメリット、撤回の可否を解説!
- 2023.11.06相続全般「死んだら財産をあげる」相続における口約束はトラブルのもと!事例をもとに解決方法を解説
- 2023.07.18遺言書作成・執行遺言書を紛失した場合にはどう対応すればいいか?
- 2023.06.30相続税申告・対策死亡退職金は相続税の課税対象になる?
無料