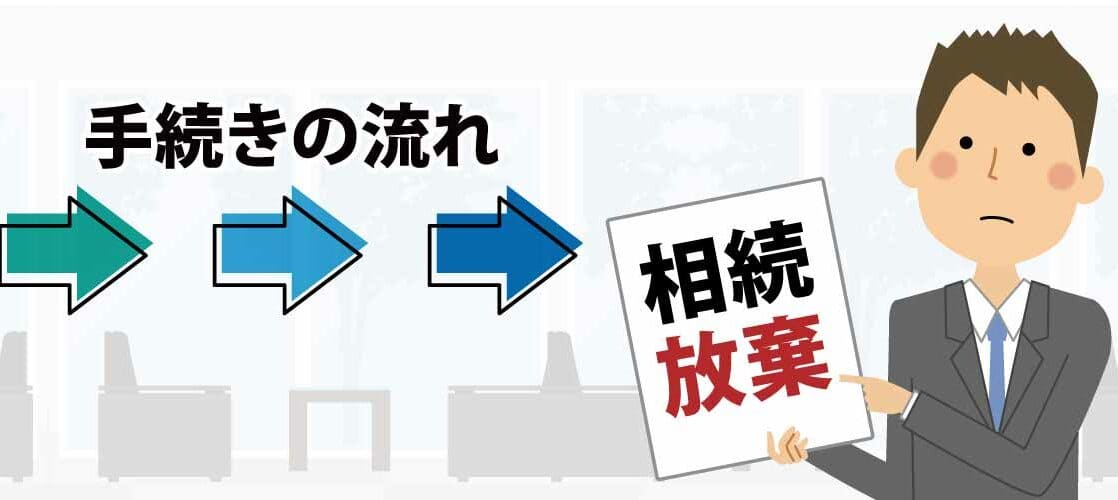- 相続放棄をするには所轄の家庭裁判所に申立てをする
- 相続放棄は原則として、相続を知ってから3ヶ月以内にしなければならない
- 3ヶ月以内に相続放棄できそうにない場合は、裁判所に延長の申立てをする方法がある
【Cross Talk 】相続放棄の手続きはどうやってするの?
親の遺産は欲しくないので相続放棄をしようと思うのですが、どうやって手続きをすればいいですか?
相続放棄をするには、管轄の家庭裁判所に申立てをします。申立てには所定の申立書や添付書類などが必要です。相続放棄は手続きできる期間が限定されている点に注意してください。
相続放棄をするには、裁判所に申立てをする必要があるんですね。相続放棄できる期間についても教えてください!
生前に仲が悪かったり、借金などの債務が多かったりなど、被相続人の遺産を相続したくない場合があります。遺産を相続したくない場合は、相続放棄という手続きをすれば、遺産を相続せずにすみます。 しかし、どうやって相続放棄をすればいいのか、いつまでに手続きをすればいいのかが、分からない場合も少なくないでしょう。 そこで今回は、どうやって相続放棄をするのか、手続きの流れに沿って解説していきます。
基本的な相続放棄の手続きの流れ

- 相続放棄をする前に、被相続人の遺産や相続人などの調査を行うことが重要
- 相続放棄をするには管轄の家庭裁判所に申立てをする
相続放棄をしたいのですが、どのような手続きの流れになりますか?
まずは本当に相続放棄が必要かを調査したうえで、管轄の家庭裁判所に相続放棄の申立てをします。申立てにおいては、申立書や添付書類などを提出しなければなりません。
遺産・相続人などの調査を行う
相続放棄の手続きをする前に、まずは遺産や相続人などの調査を行いましょう。 遺産や相続人などを調査する理由は、本当に相続放棄をすべきかどうかを検討するためです。調査の主なポイントは以下の通りです。
・被相続人(亡くなった方)の通帳や権利証などの場所や内容
・被相続人が居住していた不動産の名義
申立書の作成・申立てに必要な添付書類を収集する
相続放棄をすると決めたら、申立書の作成と添付書類の収集をしましょう。 申立書は「相続放棄申述書」などの名称で書式が定まっており、裁判所のホームページなどでダウンロードできます。申立書には主に以下のような情報を記載します。
・被相続人の本籍・最後の住所・氏名・生年月日など
・法定代理人の住所・電話番号・氏名など(申述人が未成年者の場合)
・相続の開始を知った日・相続放棄の理由・遺産の概略など
相続放棄に必要な一般的な添付書類は、以下の通りです。
・相続放棄する方の戸籍謄本
家庭裁判所に申立てを行う
申立書を作成し、添付書類を収集したら、家庭裁判所に申立てを行います。 相続放棄の申立てができる期間は、原則として、自己のために相続の開始があったことを知ったとき(原則として、被相続人が亡くなったことを知ったとき)から3ヶ月以内です。 例外が認められる場合はありますが、できるだけ上記の期間内に申立てをするようにしましょう。申立てをする家庭裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。 申立てに必要な費用として、収入印紙800円分を申立書の指定欄に貼り付ける必要があります。 また、連絡用の郵便切手が必要な場合があるので、事前に管轄の家庭裁判所に確認しておきましょう。
家庭裁判所からの照会書に回答する
相続放棄の申立てが受理された後、家庭裁判所から照会書が送られてくる場合があります。 照会書は相続放棄の申立てが本人の意思で行われているか、相続人になったことをいつ知ったかなど、家庭裁判所が確認したいことがある場合に送られます。照会書の内容はケースによって異なりますが、一例は以下の通りです(ここに記載した以外の事項についても確認される場合もあります)。
・相続人になったことをいつ知ったか・知った理由
・相続放棄をする具体的な理由
・被相続人の遺産を処分したことがあるか
裁判所から相続放棄申述受理通知書を受け取る
相続放棄が認められた場合、裁判所から「相続放棄申述受理通知書」という書類が送付されます。通知書は相続放棄が行われたことを証明する書類で、一般に以下のような情報が記載されています。
・事件番号と事件名
・申述人と被相続人の氏名
・相続放棄が受理された年月日
通知書は被相続人の債権者などに提示する場合があるので、大切に保管しましょう。 また、相続放棄の郵送手続きに使用するために提出した郵便切手のうち、未使用の分が通知書とともに返還される場合があります。
債権者に写しを送付する
生前に被相続人に金銭を貸していた業者など、被相続人の債権者に対して、相続放棄申述受理通知書の写しの送付が必要になる場合があります。 被相続人の遺産を普通相続した場合、借金などの債務も相続することになるので、被相続人の債権者から借金を返済するように請求を受ける場合があります。相続放棄をした場合は、被相続人の債務を相続していないので、被相続人の債権者に対して債務を弁済する義務はありません。 しかし、相続放棄をしたことを債権者に対して証明するために、相続放棄申述受理通知書の写しを送付する場合があるのです。
相続放棄の手続きとして知っておくべきこと

- 相続放棄の期間を過ぎてしまいそうな場合は、延長の手続きをする
- 3ヶ月の期間を超えてしまった場合は、上申書を提出する
3ヶ月の期間内に相続放棄が間に合いそうもありません。延長する方法はありますか?
3ヶ月の期間内に間に合いそうにない場合は、裁判所に期間の延長の申立てをする方法があります。また、あくまで例外ですが、期間を超えた場合も認められるケースがあります。
3ヶ月の期間内に間に合わなさそうなときには熟慮期間伸長をする
3ヶ月の期間内に間に合わなさそうな場合には、熟慮期間を伸長(延長)する方法があります。 熟慮期間を伸長するには、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをしなければなりません。 申立てをするには所定の申立書・添付書類(相続放棄の場合と基本的に同様です)・収入印紙800円分・郵送用の郵便切手などが必要です。注意点として、熟慮期間の伸長の申立ては、相続の開始を知ったときから3ヶ月以内にしなければなりません。 伸長が必ず認められるとは限らないので、なるべく早めに申請することをおすすめします。
3ヶ月を超えてしまった場合には上申書を提出して申立てをする
相続放棄をせずに3ヶ月を超えてしまった場合は、上申書を提出して申立てをすることで、相続放棄を認めてもらえる場合があります。ただし、3ヶ月を超えてなお相続放棄が認められるのはあくまで例外であり、一般に以下の2点を満たす特別な事情が存在しなければなりません。
・遺産の有無を調査することが著しく困難な事情があり、遺産がないと信じたことについて相当な理由があること
上申書に決まった書式はありませんが、上記の要件を満たすような事情があることを、具体的に示すことが重要です。 上申書を提出する方法はあくまで例外であり、必ず認められるとは限らないので、相続問題の経験が豊富な弁護士に相談して対応してもらうことをおすすめします。
まとめ
相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをしなければなりません。 申立てには所定の申立書・戸籍謄本などの添付書類・所定の収入印紙などが必要です。 相続放棄できる期間は原則として、相続があったことを知ってから3ヶ月以内です。間に合いそうにない場合は、早めに伸長の申立てをしましょう。 もし期間を過ぎてしまった場合でも、例外として相続放棄が認められるケースがあるので、相続問題の経験が豊富な弁護士に相談することをおすすめします。

この記事の監修者
最新の投稿
- 2024.03.22成年後見成年後見・任意後見・家族信託を比較しよう!
- 2023.11.28相続放棄・限定承認親の借金・債務を相続したくない場合の相続対策
- 2023.10.22遺産分割協議遺産分割審判とは?遺産分割審判に対する即時抗告とは?
- 2023.08.11相続全般一人っ子の相続で気を付けるポイントとは?弁護士が解説
無料