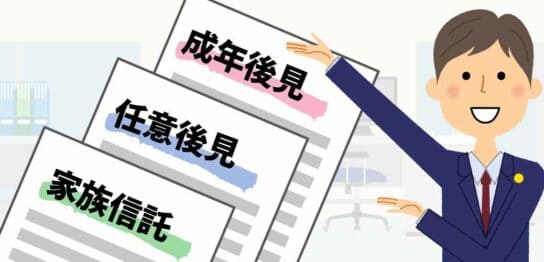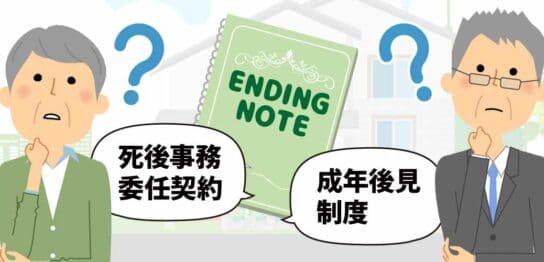- 成年後見・任意後見・家族信託のそれぞれの概要
- 成年後見・任意後見・家族信託の比較
- 人によってどれを利用するのがいいのか分かれるので専門家に相談すべき
【Cross Talk 】成年後見・任意後見・家族信託のどの制度が良いでしょうか
私の老後のことでご相談があります。自分も高齢で、認知症にかかってしまったような場合のことを考えていますが、いろいろと情報を調べていると成年後見・任意後見・家族信託というものの利用を検討すべきかな…と思っています。
それぞれ利用するシーンや目的などに違いがあるので、3つの制度を比較してみましょうか。
是非お願いします!
いわゆる「終活」をしていると、相続とは別に自分の老後・終末期について滞りなく生活ができるようにするための制度として、成年後見・任意後見・家族信託という言葉を耳にする方も多いと思います。これらの制度は一見人の終末期から亡くなって相続を見据えたときに利用するもののようにも思えますが、それぞれ利用シーンや目的などに違いがあるものです。 このページでは成年後見・任意後見・家族信託の3つの制度を比較してみようと思います。
成年後見・任意後見・家族信託の概要

- 成年後見とは
- 任意後見とは
- 家族信託とは
成年後見・任意後見・家族信託それぞれどのようなものなのでしょうか。
まずは3つの制度の概要について確認してみましょう。
まずは、成年後見・任意後見・家族信託の3つの制度がどのようなものか、その概要を確認しましょう。
成年後見とは
成年後見とは、本人が契約など法律行為をするための判断能力がなくなってしまったときに、成年後見人という保護者をつけて、本人の財産を保護するための制度です。 スーパーで食料を購入する、病院で治療を受ける、雇用契約を結んで働くなど、日常生活を送るにあたっては、契約などの法律行為は欠かせません。 しかし、認知症・精神疾患・加齢などによって、日常生活でこれらの契約をするにあたっての判断能力が落ちる・無くなってしまうということがあります。自分のした契約の内容を把握する能力のことを意思能力と呼んでいますが、意思能力のない者が行った法律行為は無効とされています(民法3条の2)。 幼児のような未成年者に親権者がつけられているように、成人した後に意思能力がなくなった場合にも後見人という保護者をつけて本人を保護しようとしたのが成年後見です。 成年後見には、裁判所が後見人を選任する法定後見と、後見人を自分で決められる任意後見に分かれます。
任意後見とは
任意後見とは、成年後見の一種で、判断能力を失う前に任意後見契約という契約を後見人となる者と結んでおき、判断能力がなくなったときにその人に後見人になってもらう制度をいいます。 法定後見は、判断能力が無くなった時点で親族などが家庭裁判所に申立てをするので、本人はそのときにはすでに正常な判断ができる状態ではなくなっています。 任意後見は、判断能力があるうちに、あらかじめ後見人となる人を自分の意思で選んでおける制度です。家族信託とは
家族信託とは、自分の財産の管理や処分を家族に任せて運用をお願いして、自分や家族が資産から発生する利益を受け取ることができるようにする契約のことをいいます。 成年後見・任意後見が裁判所に申立てをして後見人が保護者としてつくという手続きであるのに対して、家族信託は財産に関する信託契約をするものです。成年後見・任意後見・家族信託のメリット・デメリット

- 成年後見のメリット・デメリット
- 任意後見のメリット・デメリット
- 家族信託のメリット・デメリット
成年後見・任意後見・家族信託にはそれぞれどんなメリット・デメリットがありますか
それぞれのメリット・デメリットを確認しましょう。
成年後見のメリット・デメリット
成年後見のメリット
成年後見を利用するメリットとしては次の2つが挙げられます。 ・成年後見人が本人の代理人として法律行為や手続きを行うことができる・日常生活に関する行為以外の本人の行為を取り消すことができるので本人が理解しないまま契約をしてしまった場合に被害の回復が可能
成年後見を利用すると本人の代理人として法律行為をすることができるので、本人の生活・療養介護に必要な契約を完全に行うことができます。 また、判断能力が無くなってしまっており契約内容をきちんと理解できないまま契約してしまった場合に、成年後見人が取消権を行使して被害を取り戻すことができるのもメリットといえます。
成年後見のデメリット
一方で成年後見には次のようなメリットもあります。・手続きが煩雑で時間がかかる
・本人が成年後見人を決められない
・成年後見人に対して報酬を支払わなければならない場合がある
・成年後見人に与えられている権限が狭い
成年後見人の選任は、利害関係人が家庭裁判所に申立てをして行うことになります。そのため手続きが煩雑であり、長いと3ヶ月程度時間がかかります。 また、本人が判断能力を喪失した後に行われる手続きなので、本人が成年後見人となる人を決めることができません。 成年後見人に専門家や会社になってもらう場合には、報酬を支払う必要があることもデメリットでしょう。 また成年後見は本人の日常生活や療養介護のサポートを行うための権限しか与えられないので、本人の資産について運用して利益を出すような行為をすることができない点もデメリットでしょう。
任意後見のメリット・デメリット
任意後見のメリット
・本人が任意後見人を決めることが可能・任意後見人の事務を決めることができる
・手続きが成年後見に比べると簡易である
・成年後見に比べてかかる費用が少ない
任意後見の場合、判断能力があるうちに任意後見人と契約を行うので、本人が後見をしてくれる人を決めることが可能です。 また、任意後見で行う内容も事前に決めておくことができるので、成年後見ではできない財産の運用なども行うことができます。 任意後見は成年後見に比べると手続きが簡易であることから、かかる費用も成年後見に比べると安いです。
任意後見のデメリット
一方で任意後見には次のようなデメリットもあります。・本人の判断能力が低下した後には利用できない
・任意後見人には取消権がない
・亡くなった後の事務については別途契約が必要
任意後見は任意後見人となる人と事前に契約を結んでおく必要があり、本人の判断能力が無くなってしまった後では利用できません。 また、任意後見人には成年後見人のような取消権が与えられていないため、詐欺・消費者被害にあった場合の取り消しができません。 さらに、亡くなった後の事務について任意後見では定めることはできないので、別途死後事務委任契約が必要です。
家族信託のメリット・デメリット
家族信託を利用するメリット・デメリットとしては次のようなものがあります。家族信託のメリット
・信託契約の内容によって財産管理が自由に行える・財産を委託する相手を決めることができる
・手続きが比較的容易
・かかる費用が比較的安い
信託契約の内容次第で、その人に合わせた財産管理を自由に行うことができ、委託者の死後についても効力を発生させることができます。 また、信託契約を委託する相手方については契約で自由に決めることができます。 手続きが比較的容易なので、かかる費用が比較的安いのも特徴です。
家族信託のデメリット
家族信託のデメリットには次のような点が挙げられます。・判断能力を失った後には利用ができない
・受託者が本人の代理人として契約などを行えるわけではない
・委託者と受託者の2者間の契約なので他の相続人などとトラブルになる可能性がある
家族信託は信託契約を結んで行うものになるので、本人が判断能力を失った後には利用できないのは任意後見と同様です。
また、受託者は成年後見・任意後見のように代理人に選任されるわけではないので、例えば委託者を施設に入所させるための契約については行うことができません。 さらに、家族信託については委託者と受託者が契約して行うもので、その契約の内容が相続人などの希望に沿わないような場合には、トラブルになる可能性があります。
成年後見・任意後見・家族信託の違いを比較

- 成年後見・任意後見・家族信託の違いを比較
- どの手続が良いかはそのときの本人の状況・資産の内容によって異なるので迷ったならば相談を
成年後見・任意後見・家族信託の違いはどのようなところにありますか?
いくつか特徴的な違いを確認しましょう。
成年後見・任意後見・家族信託の手続きの違いについていくつかの項目で比較してみましょう。
誰が財産を管理するか
この3つの手続きで誰が財産を管理するかについて確認しましょう。 成年後見・任意後見は、ともに後見人となる人が財産を管理します。 このときに本人の財産は、原則として全て後見人が管理することになります。 家族信託の場合には、財産を受託される受託者がこれを管理することになります。 なお、家族信託の場合に管理する財産は信託契約の対象となった財産のみなので、信託契約の対象とならなかった財産については、引き続き本人が管理をすることになります。対策が可能な時期
老後・終末期の対策として利用が可能な時期について比較してみましょう。 任意後見・家族信託はともに任意後見契約・信託契約を結ぶ必要があります。 そのため、有効な法律行為ができる時期までに行う必要があり、例えば認知症が進んでしまって意思能力が無くなった後ですと利用をすることができません。 この場合には成年後見(法定後見)が利用できるにとどまります。不動産を処分すること
どの制度を利用するにあたっても不動産の処分をすることは可能です。 ただし、法定後見については、居住用の不動産の売却については家庭裁判所の許可が必要となります(民法859条の3)。誰が監督をするか
ひとたび財産を預かった人が適切に財産の管理をするか監督するのは誰でしょうか。 成年後見の場合には基本的には家庭裁判所が監督をすることになっており、成年後見人は年に1回家庭裁判所に報告をする中で業務を監督されます。 資産が多いような場合や、利害関係人が多い場合には、成年後見人を監督する立場となる成年後見監督人がつけられます。任意後見人には常に任意後見監督人がつけられ、家庭裁判所への報告も行います。 これに対して家族信託の場合には、あくまで契約者が契約内容が履行されているかを確認できるのみです。
どの手続きが誰に向いているかは人によるので専門家に相談をする
以上のような違いがある手続きですが、どの手続きが良いかは人によって異なります。 上述したように、すでに判断能力を失っているような場合には、任意後見・家族信託の利用はできません。 特定の資産のみ家族信託を利用するのがいいのか、任意後見でまるごと見てもらうのがいいのかも、どのような資産を有していて、どのような家族構成になっているのかによって異なります。 場合によっては、これらにあわせて死後事務委任契約や遺言書も併せて利用すべきになります。一つ一つのメリット・デメリットだけで判断してしまって、トータルで見るとうまく行かない・損をするということがないように、専門家にご相談いただくことをおすすめいたします。
成年後見・任意後見・家族信託にかかる費用

- 成年後見にかかる費用
- 任意後見にかかる費用
- 家族信託にかかる費用
成年後見・任意後見・家族信託についてはそれぞれどのくらいの費用がかかるのでしょうか。
それぞれにかかる費用について確認しましょう。
成年後見にかかる費用
成年後見にかかる費用としては次のようなものが挙げられます。成年後見の申立てにかかる費用
成年後見は裁判所への申立てによって行われるので次の費用がかかります。・申立て手数料(収入印紙で納める):800円
・後見登記手数料(収入印紙で納める):2,600円
・予納郵券(家庭裁判所が指定する切手を購入して納める):約4,000円程度
申立て書には書類の添付が必要でその書類の収集に次のような費用がかかります。
・本人の戸籍謄本、住民票または戸籍附票の手数料:1通につき300円程度
・成年後見等の登記が既にされていないことの証明書の手数料:300円程度
裁判所が本人の判断能力について、医師による鑑定を行う場合には、5万円~10万円程度の費用が必要です。
手続きを弁護士に依頼する場合の費用
手続きを弁護士に依頼する場合には、10万円~30万円程度の費用が必要です。専門家に成年後見人になってもらう場合
専門家に成年後見人になってもらう場合には月3万円~6万円程度の報酬の支払いが必要です。任意後見にかかる費用
任意後見にかかる費用には次のようなものが挙げられます。任意後見契約の公正証書を作成する費用
任意後見契約は公正証書の作成が必要とされています。 その費用には次のような費用が必要です。・公証役場の公正証書作成手数料:11,000円
・法務局に収める収入印紙代:2,600円
・登記嘱託手数料:1,400円
・公正証書の正本・謄本の作成手数料:1枚250円
・書留郵送料:送付書類の重量による
およそ2万円程度かかると考えておけば良いでしょう。
任意後見監督人の選任をするための手続きの費用
本人が判断能力を失った後に任意後見監督人の選任をするための手続き費用として次のような費用が必要です。・申立て手数料(収入印紙で納める):800円
・後見登記手数料(収入印紙で納める):1,400円
・予納郵券(家庭裁判所が指定する切手を購入して納める):家庭裁判所によって約4,000円程度
手数料自体は約6,000円程度となります。 専門家に手続きを依頼した場合には、10万円~15万円程度が報酬となります。 なお、本人の判断能力について家庭裁判所が判断をするために医師による鑑定をする場合には、10万円~15万円程度の費用が加算されます。
任意後見人や任意後見監督人に支払う報酬
任意後見人や任意後見監督人に支払う報酬としては次のような費用が必要です。・任意後見人
・親族がなるような場合:無償とすることも可能
・専門家(弁護士や会社など)がなる場合:月3万円~5万円程度
・任意後見監督人:月1万円~3万円程度
家族信託にかかる費用
家族信託にかかる費用としては次のような費用が考えられます。家族信託契約書を公正証書で作成するための費用
家族信託契約書を公正証書で作成するための費用として、信託財産の価格に応じた費用が必要です。| 目的の価格 | 手数料 |
| 100万円以下 | 5,000円 |
| 100万円を超え200万円以下 | 7,000円 |
| 200万円を超え500万円以下 | 11,000円 |
| 500万円を超え1,000万円以下 | 17,000円 |
| 1,000万円を超え3,000万円以下 | 23,000円 |
| 3,000万円を超え5,000万円以下 | 29,000円 |
| 5,000万円を超え1億円以下 | 43,000円 |
| 1億円を超え3億円以下 | 43,000円に超過額5,000万円までごとに13,000円を加算した額 |
| 3億円を超え10億円以下 | 95,000円に超過額5,000万円までごとに11,000円を加算した額 |
| 10億円を超える場合 | 249,000円に超過額5,000万円までごとに8,000円を加算した額 |
不動産を信託財産とする場合の不動産登記の登録免許税
不動産を信託財産とする場合には、不動産登記が必要となるので登録免許税を納める必要があります。 不動産の登録免許税としては、固定資産評価額の0.4%(土地の場合令和8年3月31日までは0.3%)が必要となります。手続きを専門家に依頼した場合の費用
家族信託は非常に高度な内容で専門家に依頼しながら行うことが多いです。 専門家に依頼する場合には次のような費用が考えられます。・家族信託の内容についてのコンサルティング(信託財産の1%程度)
・公正証書の作成(5万円~15万円信託財産の範囲による)
・不動産の登記手続き(5万円~15万円程度)
まとめ
このページでは、成年後見・任意後見・家族信託の違いについてお伝えしてきました。 終活でよく名前を聞くこれらの制度ですが、人によってどれを利用するのがいいのかは、場合によっても異なります。 判断能力を失ってしまってからでは、対策できる選択肢が少なくなってしまうので、早めに弁護士に相談をしてみてください。

この記事の監修者
最新の投稿
- 2024.03.22成年後見成年後見・任意後見・家族信託を比較しよう!
- 2023.11.28相続放棄・限定承認親の借金・債務を相続したくない場合の相続対策
- 2023.10.22遺産分割協議遺産分割審判とは?遺産分割審判に対する即時抗告とは?
- 2023.08.11相続全般一人っ子の相続で気を付けるポイントとは?弁護士が解説
無料