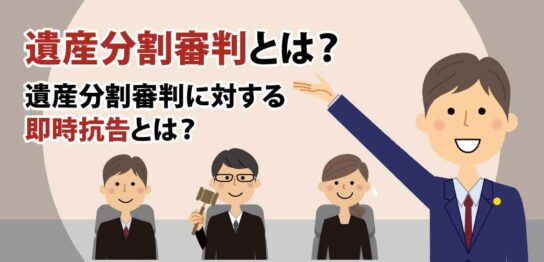- 不動産があると揉めやすい
- 寄与分や特別受益を認めるかどうかで揉める
- 遺族が揉めないように遺言書を作成する
- 揉めてしまったときは弁護士に相談する
【Cross Talk】遺産相続で揉めたくない!どうすればいい?
父が亡くなって、母や兄弟たちと相続することになりました。相続と言っても自宅と少しの預貯金がある程度でそれほどの遺産はないので、揉めずにすんなり終わりますよね?
そううまくいくとは限りません。不動産のように分けにくいものがある場合には、相続人間で意見が合わず、揉めてしまう可能性があります。また、特定の相続人が多額の贈与を受けていた場合には、法律で決められた割合(法定相続分)で分けるのは不公平だといって揉めることもあります。
遺産がそれほどなくても揉めることがあるんですね。どうすれば揉めずに済むか教えてください!
皆さんの中には、遺産相続について「うちには大した財産はないから揉めないだろう」とか、「法律で決められたとおり分ければ揉めないだろう」と考えている方が少なくないかもしれません。 しかし、統計によれば家庭裁判所で遺産分割調停が成立した事件のうち約4分の3は遺産の額が5,000万円以下であり、相続で揉めるのはいわゆる資産家だけとはいえません。
また、特定の相続人が、亡くなった方(被相続人といいます)から贈与を受けていたり、逆に相続人が被相続人に経済的援助をしていたりする場合もあり、単純に被相続人が亡くなった時点で保有していた遺産を分けるだけでは不公平だといって揉めてしまうこともあります。
そこで今回は、遺産相続で揉めるのはどのような場合かを紹介したうえで、遺産相続で揉めないための対処法などについて解説いたします。
遺産相続で揉める場合

- 遺産相続で揉める場合
- 遺産相続で揉める場合と揉めない場合の差
遺産相続で揉める場合はどのような場合でしょうか。揉める人と揉めない人には何か差があるのでしょうか。
遺産相続で揉める場合をもとに考えてみましょう。
遺産相続が原因で揉める場合
遺産相続が原因で揉める場合にはどのような場合があるかを検討しましょう。揉めている場合は遺産が5,000万円以下の割合が高い
裁判所がまとめた平成30年度司法統計 家庭裁判所の遺産分割事件によって遺産が分割された総数は7,507件です。そのうち、遺産の総額が1,000万円以下の事件が2,467件、1,000万円超5,000万円以下の事件が3,249件であり、両者の合計は5,725件となり、遺産分割事件総数の約76%を占めることになります。家庭裁判所の遺産分割事件で遺産が分割されたということは、言い換えれば遺族の話し合いだけでは解決せず、事件が裁判所に持ち込まれたということですから、相続で揉めた場合といっていいでしょう。 上記の司法統計のデータからは、遺産相続で揉めるのは資産家に限ったことではなく、多くの家庭において遺産相続で揉める可能性が十分にあるということがいえます。
不動産がある場合
また、前記の司法統計によれば、遺産に不動産(土地・建物)を含まないケースは「現金等」1,203件、「動産その他」57件、「現金等・動産その他」124件の合計1,384件であり、全体の約18%にすぎず、残る事件は、遺産に土地または建物あるいはその両方が含まれています。
つまり、遺産に土地や建物といった不動産がある場合、遺産相続で揉めやすいということがいえます。 その理由としてまず考えられるのは、不動産は現金等と異なり、現物を分けることが難しいということがあります。
建物の現物を相続人で分けるわけにはいきませんし、土地を細分化することも現実的ではないでしょう。
そうなると、相続人の誰かが不動産を取得するか、売却してお金で分けることを考えざるを得なくなり、どのように分けるかで相続人の間で意見が対立してしまうおそれがあるのです。
また、不動産は、現金等と異なり、金銭的評価が問題になります。 このような理由から、遺産に不動産が含まれる場合には、揉めやすい傾向があるのです。
相続人の一人が遺産を使い込んでいる
一部の相続人が、被相続人の預貯金を引き出し、葬儀費用や入院費、施設代などに充てることは珍しくありません。 使途を明らかにできれば他の相続人も納得するでしょうが、使途が不明な場合、相続人自身が使い込んだなどと言われ、揉める可能性があります。
子どもの遺産分割割合で揉める
被相続人に子どもが複数いる場合、子どもの相続分を子どもの人数で平等に分ければいいだけではないかと思われるかもしれませんが、実際にはそう簡単にはいきません。
例えば、被相続人に農業などの家業があり、長男が家業を継いでいた場合に、長男が他の兄弟に対し相続放棄を求めるということがあります。
また、配偶者との間の子どものほかに、前の配偶者との間に子どもがいたり、認知した子どもがいたりする場合、兄弟といっても全く交流がないことも珍しくないので、揉めやすいといえるでしょう。
介護などによる寄与分で揉める
遺産相続の割合は、法律で決められています(法定相続分といいます)。
しかし、例えば一部の相続人が長年にわたって被相続人の介護をしたり、家業を手伝ったりしていた場合、遺産相続にあたってその貢献を一切考慮しないのは不公平ではないかと考えられます。
そこで作られた制度が、「寄与分」です。 寄与分とは、被相続人の遺産の維持または増加について特別の寄与をした相続人に対し、その貢献に応じて法定相続分に寄与分を加えて遺産を取得させるというものです。
寄与分の趣旨自体はわかりやすく、公平の理念にかなうものと思われるかもしれません。
しかし、どの程度の貢献をすれば「特別の」寄与にあたるのか、仮に「特別の」寄与にあたるとしてもそれをどのように金銭的に評価するかといった問題は、簡単に答えが出るものではありません。
そのため、一部の相続人が寄与分を主張すると、揉める原因となることが多いのです。
結婚式費用を支払ってくれたなどの特別受益で揉める
寄与分は、相続人が被相続人に貢献した場合に相続人の間で公平を図るための制度ですが、逆に相続人が被相続人から贈与などの利益を受けていた場合に相続人の間で公平を図るための制度が、「特別受益」です。
特別受益とは、相続人が被相続人から遺贈を受けたり、婚姻・養子縁組・生計の資本として贈与を受けたりすることをいいます。
特別受益がある場合、被相続人の遺産にその贈与の額を加えたものを遺産とみなして相続分を計算し、相続人はその相続分から特別受益の価額を差し引いた額を取得することになります。
一部の相続人が他の相続人に特別受益があると主張した場合、そもそも贈与を受けてないとか、特別受益にあたらないなどと反論されることが考えられますので、揉めることが多いでしょう。
相続人の間で問題がある場合
相続人の間で問題がある場合はどうしても争いになりがちです。相続人同士の仲が悪い
相続人同士の仲が悪いような場合にはどうしても争いになりがちです。
例えば何かの売買契約の取引当事者間で、法律の適用の有無や契約上の権利・義務の有無を争うような場合には、問題となるのは契約に関する事項であることが多いです。
これに対して、相続人同士で争いになっているような場合には、長年家族として暮らしてきた関係性に問題があることが多く、権利・義務以上に日頃の感情が交渉に影響してしまいます。
そのため、極端な例だと「遺産は全部自分がもらう」「あなたには遺産は1円もあげない」など、客観的には無理な主張をする相続人が出てくるようなこともあります。
家族が知らない相続人が発覚する
家族が知らない相続人がいたような場合にも、遺産分割で揉めることが多いです。
例えば、結婚を複数繰り返している場合、前の結婚相手との間に子どもがいて、普段から交流が全くない結果、現在の家族が全くその存在を把握していないことがあります。
前婚での子どもも、被相続人の子どもである以上は相続人となるので、相続人調査をして知らない子どもがいることが分かると、その子どもと遺産分割協議を行うことになります。
このように、家族が知らない相続人がいて、その相続人が権利を主張してきた場合には、全く知らない人がいきなり権利を主張してくることに反感を持つと考えられるため、揉めてしまうことがあります。
遺産相続で揉めないための対策

- 遺言書を作成するのが最善の対策
- 遺言書を作成しても揉め事を完全に防止することはできない
遺産相続で揉めないようにするにはどうしたらいいですか?
生前に遺言書を作成しておくことが一番です。ただし、遺言書の効力で争いになることもあるので、遺言書を作成しても、揉める可能性をゼロにすることはできません。
遺言書を作成して相続人同士で揉めるのを防ぐ
遺産相続で揉めないようにするためには、生前に遺言書を作成しておくことが最善といえます。
寄与分や特別受益の解説で、相続人の間で公平を図るといいましたが、それはあくまで遺言書がない場合のことです。 遺言者は、遺言書によって自分の遺産の全部または一部を自由に処分することができます(ただし、後述する遺留分の問題は残ります)。 そのため、遺言書で全ての遺産について誰がどのように取得するかを決めておけば、遺産を遺言書通りに分けるだけですから、相続人が揉めることは基本的になくなります。
もっとも、これはあくまで遺言書が有効である場合の話です。 遺言書がある場合でも、偽造されたものであるとか、遺言作成時には認知症で判断能力がなかったなどとして、遺言書の効力自体が争いになることもあるので、揉め事を完全に防ぐことはできません。
また、兄弟姉妹以外の相続人には、「遺留分」という法律で保障された最低限の相続分があります。 ですから、遺言書を作成してもその内容が遺留分に配慮していないもの(例えば、一部の相続人に全財産を相続させるなど)であった場合、揉める可能性があります。
遺言書を作成する際のポイント
相続人が揉めそうな場合に、遺言書を作成するときには、公正証書遺言で作成する・付言事項を記載するようにするのがポイントです。
相続人が揉めそうな場合に、遺言書を作成するときには、公正証書遺言で作成する・付言事項を記載するようにするのがポイントです。
まず、相続人が揉めることが予想される場合には、公正証書遺言を作成することをおすすめします。
相続人が揉めそうな場合に、自筆証書遺言があるような場合には、その遺言書が本物であるかどうか、あるいは遺言者の意思に基づき作成されたものであるかどうかなど、遺言書の有効性が争われることが想定されます。
公正証書遺言は、公証人が遺言者の意思を確認して作成するため、後に無効であると判断される可能性は低くなると思われます。
そのため、公正証書遺言で遺言書を作成することが推奨されます。
また、付言事項において、自分の気持ち・願いや遺言をした経緯について記載しておきましょう。
付言事項とは、遺言書に付け足される項目で、遺言者が自分の気持ち・願いなどを自由に記載できる部分です。
この部分に、後に遺産分割で揉めないように、自分の気持ちや願い、遺言をした経緯を記載しておき、相続人に遺言書の内容を受け入れてもらうのが良いでしょう。
遺産相続で揉めたら長期化する

- 遺産相続で揉めると長期化しやすい
- 家庭裁判所に持ち込まれると1~2年かかることも多い
遺産がそれほどなくても揉めてしまう可能性があるんですね。身内といつまでも揉めていたくないので早く終わらせたいのですが…
揉め事を抱えるだけで精神的な負担になりますから、みなさんそうおっしゃいますね。
ただ、遺産分割で揉めると長期化しやすい傾向にあります。
家庭裁判所では審理期間が1~2年に及ぶことも珍しくありません。
先ほども引用した平成30年司法統計 によれば、家庭裁判所の遺産分割事件の総数13,040件(取下げ等を含む)のうち、審理期間が6ヶ月超1年以下のものが4,403件ともっとも多く、1年超2年以下のものも2,920件あります。
しかもこの期間はあくまで家庭裁判所における審理期間です。
通常、相続人の間で遺産分割協議をしてもまとまらない場合に家庭裁判所に遺産分割事件が持ち込まれるので、相続について協議を始めてからの期間はさらに長くなるはずです。
このように、遺産分割で揉めてしまうと長期化しやすいといえます。
遺産相続を弁護士に相談するメリット

- 感情的対立を避けることができる
- 面倒な手続きを全て任せることができる
遺産相続を弁護士さんに依頼したら、どんなメリットがあるのでしょうか?
感情論ではなく法的根拠に則った主張ができるということが挙げられます。また、基本的には弁護士に全ての手続を任せることができるということもメリットの一つでしょう。
感情ではなく法に則った解決策を主張してくれる
当事者だけで話し合いをすると、ついつい感情的になりがちです。そうなると、遺産相続と関係のないことで相手を非難したり、過去のことを蒸し返したりして、話し合いが一向に進展しないという事態に陥りかねません。これに対し、弁護士に相談・依頼をすれば、弁護士が依頼者に代わり、感情ではなく法に則った主張をしてくれます。
そのため、当事者だけで協議する場合と比べて、話し合いが円滑に進むことを期待できますし、専門的な知識の不足のために損をしてしまうことも防げます。
弁護士が手続を進めてくれる
遺産相続をするには、その前提として相続人や遺産などを調査することが必要で、役所で戸籍等を取り寄せたり、銀行や証券会社、法務局などを回って資料を集めたりしなければなりません。また、相続人の間で協議が整わなかった場合、家庭裁判所の遺産分割調停を申し立てることになりますが、そのためには裁判所に提出する書類を作成したり、取り寄せたりする必要があります。
これらの作業には手間と時間がかかるので相続人には大きな負担になりますし、専門的な知識が必要になる場面もありますから、相続人自身では難しいこともあるでしょう。
弁護士に相談・依頼をすれば、基本的にはこれらの手続を全て弁護士に任せることができます。
まとめ
これまで解説したとおり、相続で揉めることは決して他人事ではありません。 相続で揉めないための事前の対策や、揉めてしまった場合に早期の解決を目指すには、相続に詳しい弁護士に依頼するといいでしょう。

この記事の監修者
最新の投稿
- 2023.11.23遺言書作成・執行遺言書を無効にしたい!必要な手続きについて確認
- 2023.11.19相続全般相続人がいないいとこが亡くなった場合の相続について解説
- 2023.11.06遺留分侵害請求遺留分侵害額(減殺)請求に応じない場合に使う遺留分調停とは?
- 2023.01.25遺言書作成・執行遺言書を作成するために必要な費用は?弁護士に依頼するメリットや注意点についても解説!
無料