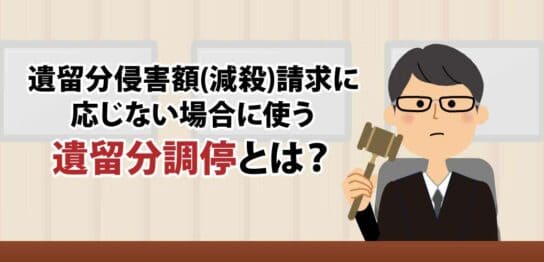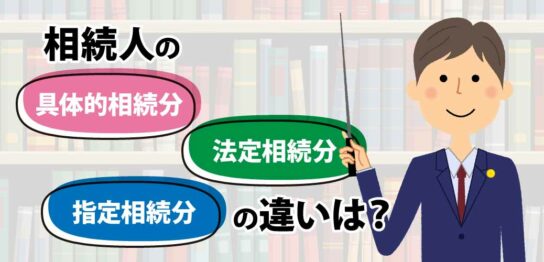- 遺留分・遺留分侵害額請求権の制度の概要
- 遺留分が原因で争いが生じるケース
- 遺留分が原因で争いが生じないようにするための対応方法
【Cross Talk 】遺言をしたことで遺留分侵害額請求を起こされ、それが元で争いにならないかが心配です。
私は個人事業主で長男が私の事業を手伝ってくれており、後継ぎにすると決めています。私もそろそろ引退という年で、長男にスムーズに事業を継がせるために、遺言を考えています。ただ、遺言によって遺留分侵害額請求をされるおそれがあると聞きました。長男の他にも独立した子どもが2人いるので心配です。
どのようなケースで遺留分侵害額請求が原因で争いになるかを知っておき、適切な対応をしましょう。
詳しくお話をきかせてください。
相続争いを避けたい、特定の相続人に相続させたい、などの理由から遺言をしておくことがあるのですが、この遺言によって相続人の遺留分を侵害した場合には、その相続人は遺留分侵害額請求をすることが可能です。そのため、遺留分という制度があることが原因で相続争いになることもあります。どのようなケースで遺留分を侵害して争いになるのか、どのような対策で争いを回避すればいいのか、を確認しましょう。
遺留分が原因でどうして争いが起きるのか

- 遺留分・遺留分侵害額請求の概要
- 遺留分の侵害によって争いがおきる原因
どのようなケースで遺留分を侵害して争いになってしまうのでしょう?
いくつかの典型的なケースがあるので確認してみましょう。
どのような場合に遺留分の侵害が原因で争いになるかを確認してみましょう。
遺留分とは
前提となる遺留分とはどのような制度かここでおさらいをします。 遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に法律上保障されている最低限の取り分で、民法1042条に規定されているものです。 法定相続分の1/2(親・祖父母など直系尊属のみが相続人である場合には1/3)が遺留分として保障されています。 被相続人の兄弟姉妹は民法1042条で明確に除外されているので、遺留分はありません。遺留分侵害額請求とは
遺贈や生前贈与によって、相続人は遺留分に相当する相続ができなくなることがあります。 このように遺留分を侵害された場合には、遺贈を受けた人・贈与を受けた人に対して、遺留分侵害額請求を行うことができます(民法1046条)。 この請求は、侵害された遺留分に相当する金銭を請求する権利であるということを確認しておいてください。遺留分の侵害によって争いが起きる原因
では遺言で遺留分の侵害によってどうして争いがおきてしまうのでしょうか。 いくつかのケースで考えてみましょう。・相続人の一人に遺産を集める
遺言で相続人の一人に遺産を集めることがあります。
本件のご相談者様のように事業を行っているような場合や、配偶者の面倒を見る同居の家族がいるような場合に後継ぎとして面倒を見てもらうのだから当然に遺産も一人で承継させるという考えに基づいて遺贈をするようなケースです。
家族間ですでによく話し合われているような場合には、遺留分を侵害するような場合でもスムーズに相続が行われることも多いのですが、被相続人と後継ぎだけで話し合って強引に行ってしまうような場合もあります。
このような場合に、納得のいかない相続人は、当然に遺留分侵害額請求権を行使することができるので、これによって争いになることが多くあります。
・相続人のことを考えずに遺言をした
中には、被相続人が相続人のことを考えずに遺言をしてしまうケースがあります。
愛人がいるために、愛人に全て相続させるような遺言や、自分が携わっていたNPO団体に全て寄付するために遺贈をする、といった遺言です。
相続人としては、このような遺言によって生活ができなくなるような場合には、遺留分侵害額請求を行使することが考えられ、これにより争いになることがあります。
・受遺者と相続人の関係が浅い
生前は遺贈について家族でよく話し合って、相続人も納得していたような場合でも、いざ被相続人が亡くなったときに、相続人自身が物入りでどうしてもお金が欲しいという場合があります。
遺言をすることには賛成していたとはいえ、実際に遺留分侵害額請求をすることができるという場合で、受遺者と相続人との関係が浅いような場合には、「もらえるものはもらっておきたい」と遺留分侵害額請求を行う場合があり、争いになるようなことが考えられます。
遺留分が原因で争いにならないために

- そもそも遺留分を侵害しない
- やむをえず遺留分を侵害する場合の対応方法
遺留分が原因で争いになるケースについてはよくわかりました。ではどのような対応をとれば良いでしょうか。
そもそも遺留分を侵害する遺言をしないのが一番の方法ですが、やむをえず遺留分を侵害する遺言をする際の注意点や、遺留分を侵害する遺言について遺言そのものを無効とする争い方をされる可能性もあるので、できる限り公正証書遺言にしておくこともおすすめいたします。
では、遺留分を侵害することが原因で争いになることへの対応方法にはどのようなものがあるでしょうか。
遺留分を侵害しない
遺留分を侵害することが原因で争いが生じるわけですから、遺言・生前贈与をする場合に遺留分を侵害しないようにするのが一番の対応方法であるといえます。 本件のご相談者様のように、特定の相続人に遺産を集める場合でも、遺留分に相当する金銭や自動車などの遺産の一部を相続させることで、そもそも遺留分侵害額請求をできないような遺言をするのが理想的です。しかし、遺産の内容(特に不動産の価額が遺産の多くを占める場合)によっては、遺留分を侵害しないような遺言をすることが難しいことが考えられますので、次のような対応方法も考えておきましょう。
やむをえず遺留分を侵害する場合でも事情を説明する
やむをえず相続人の遺留分を侵害する場合であっても、ただ遺言があって自分に遺産がない、というのと、どのような経緯・考え方で自分に遺産がないのかが説明されているのとでは、遺留分を侵害された相続人の感情に大きな違いが生じるといえます。遺言は通常は遺産をどのように割り振るかを記載するのですが、附言事項という項目でメッセージなどを自由に記載することが可能です。 また、エンディングノートと呼ばれる、終末期から死後のことについて自由に記載するもので、相続人などに自由にメッセージを伝えることができます。 どうして遺留分を侵害するような遺言になったのか、その原因や想いなどを伝えて、遺留分を侵害される相続人に納得してもらうことで、争いを避けることができる可能性もあります。
遺留分侵害額請求に対応する金銭を用意する
現実に遺留分侵害額請求をされる場合、請求をしてきた人に対して、遺贈・生前贈与によって受け取ったものをそのまま返還する必要はなく、侵害された遺留分相当の金銭の支払いをすることで解決します。 対策をしてもやむをえず遺留分侵害額請求をされた場合に備えて、これに対応することができる金銭を用意しておくことを忘れないようにしましょう。公正証書遺言で遺言を残す
遺留分を侵害するような遺言がある場合で、その内容が極端であるような場合には、遺留分について争うだけではなく、そもそもそのような遺言を本当に本人がしたのか等、遺言の有効性を争うようなことがあります。 このような争いは、遺言書の作成にあたって関わる人が少ない自筆証書遺言・秘密証書遺言がされた場合によく起こります。公正証書遺言があれば必ず有効になる、というわけではないのですが、公証人という法律の専門家である公務員が遺言書を作成し、作成にあたって弁護士や行政書士という専門職が関与し、証人の立会いも必要とされる公正証書遺言のほうが、信頼性が高いです。 遺言の有効性をめぐり無用な争いを避けるためにも、遺留分を侵害する遺言をする場合には、公正証書遺言で行うことをおすすめいたします。
まとめ
このページでは、遺留分が原因で争いになるケースとその対応方法を中心にお伝えしました。 遺留分侵害額請求権を行使されると、かならず金銭を支払う義務があり、争いになることがあるので、遺留分を侵害する遺言をするときには慎重に行うようにしましょう。

この記事の監修者
最新の投稿
- 2024.03.22成年後見成年後見・任意後見・家族信託を比較しよう!
- 2023.11.28相続放棄・限定承認親の借金・債務を相続したくない場合の相続対策
- 2023.10.22遺産分割協議遺産分割審判とは?遺産分割審判に対する即時抗告とは?
- 2023.08.11相続全般一人っ子の相続で気を付けるポイントとは?弁護士が解説
無料