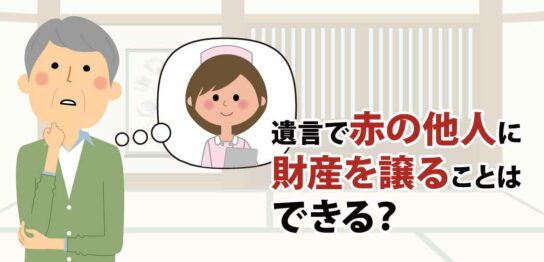- 遺言書を預けておく必要性
- 遺言書を預ける相手
【Cross Talk 】遺言書はだれかに預けておいたほうがいい?
私は相続にあたって家族が揉めないようにあらかじめ遺言書を書いておきました。この遺言書ってみなさんどうやって管理されているんでしょうか?誰かに預けた方がよいでしょうか。
自宅で管理をしていると発見されなかった時にせっかく作った遺言が台無しになってしまいかねません。そのため作成して預けておくことは望ましいといえます。誰に預けるかは人によるので是非相談してください。
是非お話しを聞かせてください。
遺言書を作成した場合に、その遺言書をどう管理しておくのが良いか、という問題が発生します。自宅で管理をしていた結果、施設への引っ越しの際・死後の遺品整理の際の不手際で紛失してしまうような事にもなりかねません。とはいえ誰かに預けておくことにより遺言書の内容が漏れて、それが原因で遺言書が破棄・改ざんされるなどの可能性もあります。どのような方法が良いのかについて検討しましょう。
遺言書は誰かに預けておく必要があるか

- 遺言書を自宅でだれにも見つからないように保管しておくと死後も誰にもみつけてもらえず破棄されるおそれ
- 誰かに預けておくと破棄・改ざんのおそれ
遺言書はだれかに預けておいた方が良いのでしょうか?持っている場合の危険・預けてしまうことによる危険それぞれ教えてもらってよいですか?
それぞれに一長一短があることは確かです。具体的に見てみましょう。
遺言書はだれかに預けておく必要があるのでしょうか。 自宅で保管をしていて発生しうる不利益と、誰かに預けておくことで発生する不利益を見てみましょう。
遺言をして遺言書を作成したとしても相続人・受遺者に届かなければ使われない
自宅の誰も空けないタンスの奥深くに遺言書を置いておいた、としましょう。 遺言書を作成した後に病気で体が不自由になり、自宅をひきはらって施設に入るときに、荷物を処分した中に遺言書が含まれてしまうようなケースも考えられます。 また、自分が亡くなった後に、遺品整理を行った際に、その遺言書が誰かの目に触れれば良いのですが、もし誰の目に触れず破棄されてしまえば、相続人・受遺者に使われません。 せっかく、争いを避けたい・自由に相続させる相手・割合を決めたいと思って作った遺言書が利用されないと作った意味がなくなってしまうと言えます。時間がたってから遺言書が見つかるようなことがあると混乱する
仮に探せばすぐに見つかるような場所においてあったとしても、時間が経ってから初めてみつかると、相続手続きが混乱することも考えられます。 たとえば、父・母・子2人というような家族で、父が亡くなった場合に、母がそのまま自宅に住んでいるような場合には、亡くなった父の荷物はそのままにしているようなこともあります。 数年後に母の体が不自由になってきたので、子の一人と同居を始めるために、実家の財産を処分している間に見つけた…という場合には、相続手続きをやりなおす、といった事にもなりかねません。 その結果、相続手続きが大いに混乱を来すという可能性があります。偽造・変造をされないように注意をする必要もある
とはいえ、遺言書を誰かに渡していると必ず安全かというとそういうわけでもありません。 遺言書の内容について相続人に漏れた場合、自分に有利な遺言をしようと、遺言書を改ざんするようなことも考えられます。 不利な内容が書かれている遺言書を発見したような場合には、そのまま遺言書を破棄してしまうこともあるかもしれません。遺言書の預け先を検討しよう

- 遺言書の預け先
- 遺言書の預け先ごとのメリット・デメリット
持っておくのも、預けるのも一長一短があるということでしょうか。預け先にはどのようなものがありますか?
遺言書を預ける先について具体的に検討をしてみましょう。
遺言書の預け先について検討をしましょう。
銀行の貸金庫などに預けておく
預金をしている銀行の貸金庫を契約して、そこに遺言書を入れておくことも一つの手です。 保管料がかかりますが、破棄されたり、改ざんされるおそれはかなり低いといえます。 貸金庫の契約を遺族が知らないような場合には、自宅で保管している場合と同様に、遺言書の存在自体知られない可能性は否定できませんので注意が必要です。 貸金庫の契約は通常当該金融機関の口座振替で行われますので、遺族が通帳の記載を見れば貸金庫の存在に気付くことができます。相続人に預けておく
遺言で一番有利な財産取得をする相続人に預けておいて、亡くなった後にその遺言を使ってもらうことも考えられます。 たとえば、父・母・長男・長女という構成で、長男が父母と同居しているような場合、父が不動産の名義を長男にするように遺言書を記載し、その遺言書を長男が預かっておくといった例が挙げられます。 遺言者が亡くなった後に確実に遺言書を使ってもらえることが期待できます。しかし、不利な内容が記載されている相続人に預けると、破棄されたり内容を改ざんされるおそれがあります。 また、有利な扱いをうける人に持たせていると、別の相続人がその有効性を争うような事にもなりかねません。 すでに家族で合意ができていて、手続きをスムーズに進める趣旨で遺言をしたような場合には、この方法をとることもできるでしょう。
相続人以外の人に預けておく
利害関係のない相続人以外の人に預けておくことも選択肢の一つです。 自分が亡くなったときに葬儀に来てくれるような方であれば、亡くなったことを知った上で相続人に手渡してくれることが期待できます。 ただ、預けておいた方が亡くなってしまったり、遺言書を紛失してしまったり、遺言者が亡くなった連絡がいかなかったような場合には遺言書を相続人に渡してもらえない、というおそれがあります。遺言執行者に預ける
遺言について遺言執行者を定めている場合には、遺言執行者に預けるのが良いでしょう。 遺言執行者とは、遺言の内容を実現する役割の人です。 遺言執行者は相続人でもなることができますので、相続人の一人に遺言執行者になってもらう事も可能ですが、一般的には弁護士などの専門家になってもらうことのほうが多いといえます。 相続人の一人に遺言執行者になってもらう場合には、相続人に遺言を預けておくことと同じようなメリット・デメリットがあり、弁護士などに依頼する場合には後述するようなメリット・デメリットがあるといえます。 遺言執行者については「遺言執行者って何をしてくれる人?つけておいたほうがいいの?」こちらで詳しく解説していますので参考にしてください。遺言書作成を依頼した弁護士などに預ける
自筆証書遺言を作成するときには、法律の規定に従って作成しないと無効になります。 また公正証書遺言を作成するときには、公証人とのやりとりがあります。 遺言をするにあたっては法律知識が不可欠といえるので、弁護士などに相談をして遺言書を作成することが望ましいといえます。 弁護士などの専門家は遺言書を保管しておいてくれることもあります。自分の死後に相続人に連絡をとってもらい遺言書を渡してもらう、あるいはその専門家に遺言執行者になってもらって事務の一切をまかせるという事もできます。 弁護士には守秘義務がありますので、遺言の内容はもちろん、遺言をしているかどうかということも秘密にすることができます。 遺言書を相続人に届け、かつ内容を秘密にして、偽造・変造を防ぐことができるものになるので、一番お勧めすることができる方法です。
自筆証書遺言書保管制度について知ろう
令和2年7月10日より、自筆証書遺言書保管制度というものが始まります。 これは法務局で自筆証書遺言書を保管しておき電子データ化しておき、死後に相続人からの請求に応じて画像にした遺言書を渡すというものです。 詳しくは「【令和2年7月10日スタート】自筆証書遺言書保管制度ってどんな制度?」こちらを参考にしてください。まとめ
このページでは遺言書の預け先についてお伝えしてきました。 作成した遺言書を相続人などに届ける、などの遺言書の保管に関する価値観を知っていただいた上で、どこに保管しておくのがベストかの参考にしていただけたと思います。 具体的な事情に基づいてのアドバイスが欲しい場合には弁護士に相談するようにしましょう。

この記事の監修者
最新の投稿
- 2024.03.22相続手続き代行遺産相続を弁護士に相談・依頼したときの流れ、準備することを解説!
- 2023.09.17遺言書作成・執行遺言書は誰に預ける?危険のない方法について弁護士が解説
- 2023.07.18相続全般独身の人が亡くなったら法定相続人は誰になる?注意点についても弁護士が解説
- 2023.07.18遺言書作成・執行遺言書に納得できない!遺言書と異なる遺産分割はできる?
無料