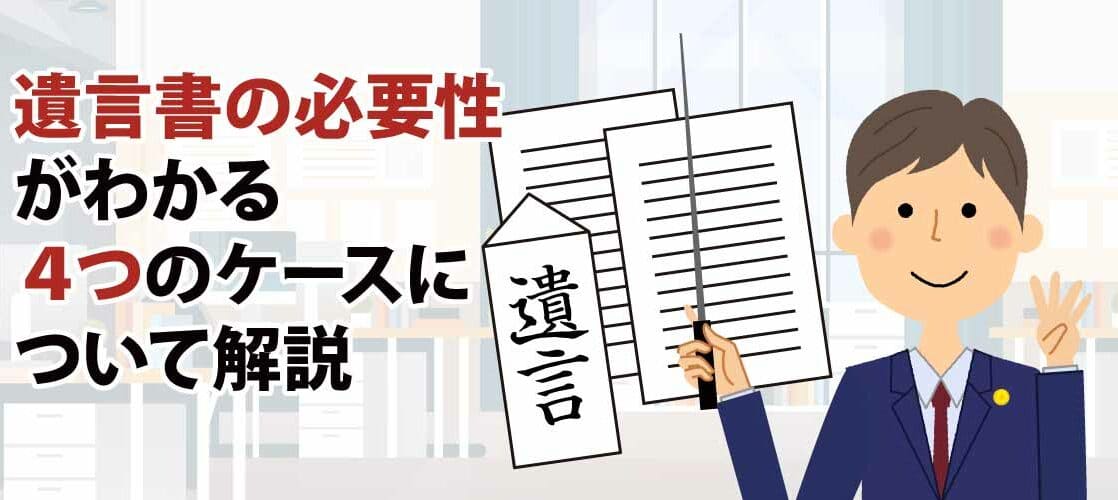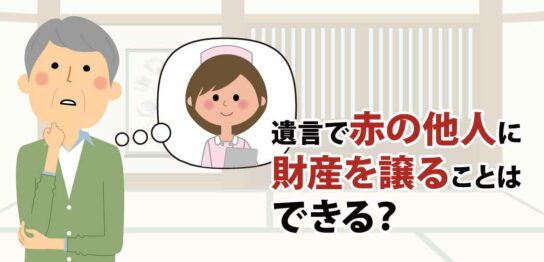- 遺言書を作成しておくと、原則として遺言書の内容に従って遺産を相続してもらえる
- 遺言書を作成しなかった場合、相続人の間で相続争いになる可能性がある
- 遺言書の必要性が高いケースは、相続人以外に遺産を渡したい場合や、相続税申告の可能性がある場合など
【Cross Talk 】遺言書を作成しておく必要性は高い?
私の遺産の整理を考えているのですが、相続人の間で相続争いにならないか心配です。また、お世話になっている友人に遺産の一部を渡したいとも思っています。
相続争いを防止するには、遺言書を作成しておく方法があります。遺言書を作成しておくことで、相続人以外に遺産を渡すことも可能です。
遺言書を作成しておくと、様々なケースで役に立つのですね。遺言書の必要性が高いケースについても教えてください!
遺言書がない場合、民法が規定する法定相続分で遺産が分割されるのが原則です。 しかし、法定相続分による場合、取り分に納得できない相続人によって相続争いになってしまう可能性があります。 遺言書を作成しておくと、原則として遺言書の内容に従って相続が行われるので、相続争いの防止に有効です。 そこで今回は、遺言書を作成しておく必要性が高いケースについて解説いたします。
遺言書を作成するとどうなるか

- 遺言書を作成すると原則として、遺言書の内容に従って相続してもらうことができる
- 遺言書を作成しなかった場合、相続人の間で相続争いになる可能性がある
私の遺産をめぐって相続人が争わないようにするには、どうすればいいですか?
遺言書をすると、原則として遺言書の内容に従って相続してもらうことができます。一方、遺言書を作成しなかった場合は、相続人の間で相続争いになる可能性があるのです。
遺言書がなければ民法の規定に従った相続
遺言書がない場合、民法の相続の規定に従った法定相続分で相続が行われるのが原則です。 例えば、被相続人(亡くなった方)に配偶者と子ども(長男と次男)がいる場合、法定相続人は配偶者・長男・次男の3人です。 被相続人の遺産が1,000万円の場合、法定相続分は配偶者が500万円・長男が250万円・次男が250万円になります。法定相続分による相続はトラブルになる可能性がある
法定相続分による相続は、遺産をめぐって相続人の間でトラブルになる可能性があります。 例えば、先程の例において、長男が「自分は父親の事業をずっと手伝って遺産を増やすのに貢献したのだから、より多くもらうべきだ」と主張するなどです。法定相続分どおりに相続する場合も、そうでない場合も遺産を相続して、受け取るためには遺産分割協議書を作成する必要があります。
しかし、遺産分割協議書の成立のためには、相続人全員で署名・押印をする必要があるので、全員が同意しない場合には遺産分割協議が成立せず、相続人の間で争いになる可能性があるのです。
遺言書の作成によって遺言書の内容による相続をしてもらうことが可能となる
遺言書を作成すると、原則として遺言書の内容に従って相続してもらうことが可能になります。 法的に有効な遺言書がある場合は、原則として遺言書の内容が優先されるからです(ただし、遺留分という最低限の取り分は保護されるので、遺言書を作成すれば全て遺言書の内容通りになるわけではありません)。例えば、先程のケースにおいて、「長男は事業に貢献してきたので、1,000万円の遺産を妻300万円・長男500万円・次男200万円で相続させるものとする」と遺言書で指定しておくなどです。 遺言書の内容が優先される結果、遺産をどう分割するかについて相続人の間で話し合う必要がなくなるので、相続争いを防止しやすくなります。
遺言書を作成する必要性が高いケース

- 遺言書を作成しておくと、相続をめぐるトラブルを防止しやすくなる
- 相続人以外に遺産を渡したい場合や、相続税申告の可能性がある場合などは、一般に遺言書を作成する必要性が高い
遺言書の作成を検討しているのですが、遺言書を作成する必要性が高いケースを教えてください。
遺言書を作成しておく必要性が高いケースは、相続人以外の方に遺産を渡したい場合や、相続税を申告する可能性がある場合などです。
相続人以外の方にも遺産を渡したい
相続人以外の人に遺産を渡したい場合は、遺言書によって遺贈をすることで、遺産を渡すことができます。遺贈とは、遺言書によって遺産の全部または一部を他人に無償で与えることです。遺贈によって遺産を渡す方を遺贈者といい、遺産をもらう方を受遺者といいます。 受遺者になれる方は特に制限がないので、遺言書によって遺贈をすることで、相続人以外にも遺産を渡すことができます。
遺贈の活用例としては、籍を入れていない内縁関係のパートナー・配偶者の連れ子(養子縁組をしていない場合)・兄弟姉妹(一定の場合には相続人になります)・お世話になった他人などです。
相続税申告をする可能性がある
遺産の合計額が多いなど、相続税の申告をする可能性がある場合は、遺言書を書いておく必要性が高いケースです。 配偶者控除や小規模宅地の特例等、相続税申告において納税額を減らすことができますが、その適用のためには、原則として申告期限内の申告が必要となります。相続税の申告は、相続開始(被相続人が亡くなったことを知ったとき)から原則として10ヶ月以内に済ませなければなりません。
申告期限を延長できるのは、相続人の異動(ある相続人が相続資格を喪失するなど)などの特殊な事情がある場合に限られます。 遺言書がない場合は、遺産分割協議が成立してから相続税の申告をしますが、相続人が揉めてしまって遺産分割協議がなかなか成立しない場合は、10ヶ月の申告期限に間に合わない可能性があります。
申告期限に間に合わなかった場合、上記配偶者控除や小規模宅地の特例を利用できず多くの納税額となったり、追徴課税として、通常よりも多くの金額を納付しなければならない可能性があったりするのです。 法的に有効な遺言書があれば、原則として遺言書に記載されたとおりに遺産が分配されるので、協議が成立せずに申告期限に間に合わないという状況を防ぎやすくなります。
まとめ
遺言書がない場合、法定相続分によって遺産が分割されるのが原則ですが、相続人の間で相続争いになる可能性があります。 遺言書を作成しておくと、原則として遺言書の内容に従って相続が行われるので相続争いを防止しやすくなるほか、遺贈によって相続人以外に遺産を渡したり,相続税申告をスムーズに行うことも可能です。 有効な遺言書によって相続をスムーズに進めたい場合は、相続問題に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

この記事の監修者
最新の投稿
- 2023.04.25遺留分侵害請求遺留分侵害額請求されたら?対処法や弁護士に相談するメリットなどを解説!
- 2022.11.27相続全般不動産(土地)を生前贈与する場合の注意点と手続きについて解説
- 2022.06.23相続全般生前贈与とは何か?他の制度との違いメリット・デメリット税金などについて解説
- 2022.05.25相続全般数次相続とは?数次相続が発生した場合の遺産分割について解説
無料