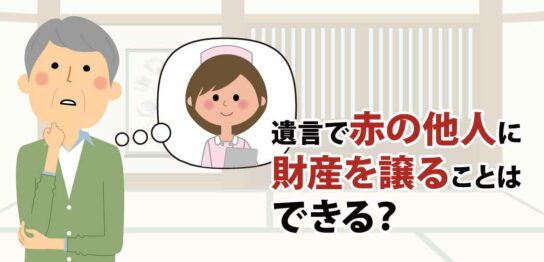- 遺言書がなければ法定相続分に従って相続をする
- 遺言書で法定相続分と異なる相続分で相続するように指定をすることができる
- 相続分の指定にあたっては遺留分の侵害に注意する
【Cross Talk 】遺言書で「相続分の指定」をするというのはどういう意味なのでしょうか。
私自身の相続についての対策を考えています。遺言書についていろいろ調べていると、「相続分の指定ができる」という事を知ったのですが、これはどのような意味なのでしょうか。
民法上定められている相続分の割合とは異なる割合で相続させることができる、という意味です。ただし、遺留分の侵害には注意しましょう。
詳しく知りたいです。
相続が発生すると、遺言書が無ければ法定相続分に従って相続をいたします。法定相続分に従った相続を望まない場合には遺言書を残して対策をするのですが、その対策の方法の一つとして相続分を指定することが挙げられます。本来であれば法定相続分に従った相続ですが、遺言書を作成しておけば相続分の割合を変えることが可能です。このページでは遺言書による相続分の指定についてお伝えいたします。
遺言書で相続分の指定をするというのはどういうことか

- 法定相続分と相続分の指定
- 相続分の指定の2つの方法
相続分の指定とはどのような意味ですか?
法定相続分とは異なる割合での相続分による相続をさせることをいい、遺言書で行います。
相続分の指定とはどのようなことを指すのでしょうか。
遺言書がない場合の相続の原則
遺言書がない場合の相続の原則について確認しておきましょう。 遺言書がない場合には民法の規定に従って相続が行われます。 民法の規定では、相続人が誰かによって異なる相続分が定められています。一般的に、この民法上の相続分を法定相続分といいます。遺言書がない場合、この法定相続分があることを前提として、相続人間で遺産分割協議を行うことになります。なお、遺産分割協議によって法定相続分と異なる割合で相続することを合意することも可能です。
しかし、相続人間で遺産分割協議による合意ができない場合、調停等の法的手続きを経たうえで最終的には法定相続分に従った相続とならざるを得ません。そうすると,たとえば私立の医大を出してもらった長男と、高校を卒業してからすぐに実家の家業を手伝っていた長女がいるようなケースでも同等に扱われることになりますが,これだと不公平だということになりかねません。なお、このような場合に備えて、法律でも特別受益・寄与分といった規定は用意されていますが、法律上具体的な金額は定められておらず、いくらの金額が認められるかはケースバイケースとなるため、事案によってはその金額の算定で争いになる場合もあります。
これらをふまえ、相続人らに法定相続分に従った相続をさせたくない場合には、遺言書を作成して対策をする必要があります。
遺言書で相続分を指定することができる
どのような形で遺言書を作成するかは、遺言者の自由です。例えば、相続人がそれぞれどのような割合で相続をするかを決めることができます。 この方法は「相続分の指定」というものです。 相続分の指定には、次の2つの方法があります。
遺言書で直接相続分を指定する
まず一つ目の方法は、遺言書の中で相続分を指定するやり方です(民法902条1項)。 遺言書の中に、各相続人がどのような割合で相続をするかを指定しておきます。相続分の指定を第三者に委託する
もう一つの方法は、相続分の指定を第三者に委託するやり方です(民法902条1項)。遺言書を作成した後に割合を変えたくなった場合、再度遺言書を作成する必要があり、手続的な負担が発生します。
そこで、相続分の指定を第三者に委託しておき、実際に遺言書者が亡くなった後に委託をした第三者に相続分を指定してもらうことが可能になっています。遺言書で相続分の指定をする際の注意点

- 遺留分の侵害となる場合に注意
- 相続債務に関する指定は相続債権者には主張できない
遺言書で相続分の指定をする場合にはどのような注意がありますか?
遺留分を侵害する内容となる可能性があることを確認しておくことと、相続債務に関する指定は相続人のみを拘束して相続債権者には主張できない点に注意しましょう。
遺言書で相続分の指定をする際の注意点はどのようなものでしょうか。
遺留分の侵害となる場合
注意点の一つ目は、内容によっては特定の相続人の遺留分を侵害する内容となる可能性がある点です。 遺留分とは、相続において民法上最低限保障されている取得分をいいます。遺言書で相続分の指定がなされていたことにより遺留分として定められている分(相続分の1/2(直系尊属のみが相続人である場合には1/3))に該当する遺産を受け取ることができない相続人は、遺言書で相続分の指定を受けていた相続人や受遺者に対して、実際に遺留分が侵害されている金額に応じて遺留分侵害額請求権を行使することができ、請求を受けた相続人や受遺者は、遺留分を侵害している金額を支払わなければならなくなります。
そのため、遺留分に注意した相続分の指定をすることが望ましいといえるでしょう。 なお、遺留分侵害額請求権を行使するかしないかは相続人の自由ですので、遺留分を侵害する内容で遺言書を作成したとしても、遺言書自体は有効となります。相続債務について指定をしても債権者には主張できない
相続というと不動産・現金・自動車など資産をどう分配するかについてのみ検討しがちです。 しかし、借金のようなマイナスの遺産についても相続することになります。例えば、遺言者が個人事業を営んでおり事業に関する借金を後継ぎになる相続人にだけ継がせたいという場合や、法人でも連帯保証債務がある場合に後継ぎになる相続人にのみ継がせたいという場合があります。 このような指定は相続人の間では効力がありますが、債権者との関係では効力を有しないので注意が必要です。
この場合、債権者との関係では、債務は相続人に法定相続分に従って承継されており、債権者はそれぞれに請求をすることが可能となります。まとめ
このページでは、遺言書による相続分の指定についてお伝えしました。 遺言書によって法定相続分とは異なる相続分の指定をすることは可能ですが、注意点もありますので、このような遺言書の作成を考えている場合には専門家に相談してみましょう。

この記事の監修者
最新の投稿
- 2024.01.22遺産分割協議法定相続人が配偶者・兄弟姉妹の場合は争いになりやすい?実例と対策について解説
- 2023.11.23相続税申告・対策借地権を相続した場合の相続税の評価の方法について
- 2023.11.19遺産分割協議相続で揉めてしまったときには裁判(訴訟)?紛争別の解決
- 2023.10.22相続全般別居中の配偶者が亡くなった場合、相続や遺留分はどうなる?弁護士が解説
無料